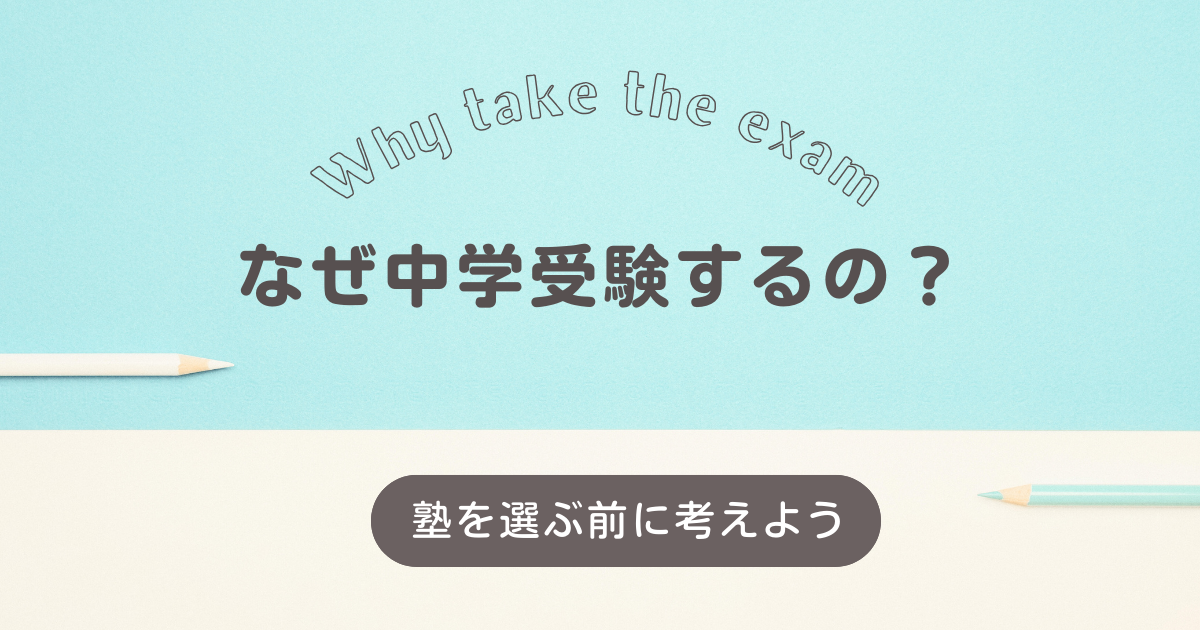
※2024.3.17加筆修正。
みなさんは、いつごろから中学受験を意識しはじめたでしょうか?
「中学受験させよう」と考えたきっかけは何だったでしょうか?
今回は、受験に向かって走り出す前に考えておきたいことを書いてみたいと思います。
1.中学受験を考え始めた時期
(1)子供が乳幼児の段階
さすがにこれは早いですね。おそらくは、両親とも私立中高のご出身で、それ以外の選択肢を考えていない、そういうご家庭でしょうか。
生徒の一人にそうした子がいました。ご両親とも都内の名門私立中高のご出身です。ご両親の兄弟もまた私立中高出身であり、さらに、祖父・祖母も同様でした。祖父母の時代に中学受験をするのはまだ少数派だったと思いますが、孫の生徒曰く「おばあちゃんとおじいちゃんは、お嬢様とお坊ちゃまだったみたい」だそうです。
進学塾の老舗の四谷大塚が創業したのが1954年、教材の予習シリーズが登場したのが1960年です。子の予習シリーズの作成により、さらに老舗であった「日本進学教室(日進)との戦いに勝利し、1970年代には、難関校受験のトップ塾として君臨していたはずです。この時代に子供を受験させたとすると、その子供が今や自分の子供を受験させる年代へとなっているのでしょう。
※四谷大塚の詳細については、以下の記事に書きました。興味のある方、懐かしい方はぜひご覧ください。
私の教室に、ある日一人の女性がご相談にみえました。20代から40代のいずれにも見える、年齢不詳の方でしたね。中学受験についての一般的な情報をお知りになりたいようなので、丁寧に対応をしていたのですが、どうも違和感があったのです。
「ところで、お子さんは何年生ですか?」
「いえ、小学生では。」
「ああ。幼稚園ですか?」
「いえ。」
「お子様はおいくつなんですか?」
「まだ生まれていません。」
ご結婚もされていないとのことでした。
早々にお引き取りいただきましたが、これはさすがに極端すぎる例ですね。
(2)幼稚園のとき
私にいわせれば、これもずいぶん早いと思います。私立小学校の受験を考えるのならわかるのですが。
もっとも、海外からのご相談で、こんど小学生になるタイミングで帰国するのだが、中学受験に有利な公立小学校を教えてほしい、というものはありましたね。どの地域に住んでもかまわないので、中学受験の実績が良い公立小学校を探しているとのことでした。
〇公立小学校の教育内容によって中学受験が有利になることはない
〇「お受験小」とよばれる、一部の私立小学校ならそういう学校もある
〇一部の公立小学校には卒業生の大半が受験をするところもあるが、その小学校だから特別な教育をしている、というわけではない
このようなお話をしたのを覚えています。
中学受験をする生徒が少ない小学校の中には、学校の先生が中学受験のための塾通いに否定的である、そういうところも残念ながらあります。いや、現在では「ありました」という過去形ですね。もう中学受験は一部の優等生だけの世界ではありませんから。とはいえ、塾通いに(心の中では)賛成していない先生もいます。受験率が高い小学校ならそういう先生が少ないことが期待できる(かもしれない)という程度のメリットしかありません。
(3)小学校低学年(1~2年)
過熱する中学受験の状況を考えると、今や一番多いタイミングが、この時期かもしれません。一部の塾の中には、低学年のうちに募集を打ち切るところもあると聞きました。入塾を希望する生徒を断るとは、またずいぶんな殿様商売だなあ、と思いますが、塾というのは、飲食店などと同様に、立地型産業の側面が強いのですね。駅前の好立地に教室を確保しなければなりませんので、入塾希望者に合わせて教室を用意するのが困難だということはいえます。また、どんなピルにも入居できるわけもありません。ビル側で大勢の子供の出入りを敬遠されるという話も聞きますし、飲食店が入るビルは教室に不向きです。自由が丘駅前のビルに入居していた某塾では、上のフロアにフラメンコ教室があるため、床を踏み鳴らす音が教室に洩れてきて困る、などという笑えない話を聞いたことがあります。仮に場所を確保できたとしても、担当教師を集めるのは、それにもまして困難です。
低学年のこの時期からの通塾は賛否両論ですね。私も手放しで推奨しかねます。通塾させるなら、以下の条件が必須でしょう。
◆塾への送迎が可能
◆自宅から歩いていける範囲に良い塾がある
◆週1回程度(多くても2回まで)
◆自宅で子供の学習を見てあげる余裕が両親にある
◆他の習い事が多くない・・・せいぜい週1~2回程度
◆塾に丸投げしない
◆先取り塾は避ける
低学年は小学校から帰ってくる時間は早いとはいえ、一人で塾の往復は難易度が高いです。昨今の社会情勢を考えれば推奨できません。親が送迎できることは必須だと思います。
これに関しては、「いつまでも親がかりではだめな子が育つ」「一人で行けるように訓練すべきだ」というご意見もあるでしょう。もちろん「共働きでは送迎など不可能だ」ということもわかります。しかし、近所の公園で低学年や幼稚園程度の子供たちが、「子どもたちだけで」遊んでいるのを見ると、親は平気なのかなあ?とこちらが心配になってしまいます。私には信じられません。残念ながら昔とは時代が違うと思うのですが。
また、電車に乗ってまで塾に行く必要性はありません。低学年の学びは、自宅でも十分可能だからです。車での送迎だとしても、塾近辺に駐車場を探す必要があります。歩いていけるレベルの近所が望ましいと思います。(送迎つきの塾というのもあるようですね。需要があれば供給があるということでしょうか。ちなみに海外の塾--アメリカ各都市・上海・ジャカルタ等--では送迎が必須です。もちろん治安の問題です。日本の治安もそちらに寄ってきているような気がします。)
さらに、最近の子供は習い事が多いですね。しかし週は7日間しかありません。その全てを習い事や塾で埋め尽くすのは賛成できません。インプットした後には、脳内でそれを熟成させる時間が必要なのです。また、学び以外の経験を積めるのもこの時期しかありません。
また、ここで「先取り塾」といっているのは、低学年のこの時期に向けた教材や授業をやらずに、高学年用の教材を先取りでやらせる塾のことです。これは時間の無駄というより思考力の発達を阻害しますので、避けたほうがよいでしょう。
(4)小学校中学年(3~4年)
従来は、小学4年の春が中学受験塾の入塾タイミングの多数派でした。今でもそれは変わらないと思いますが、何も準備なしで、いきなり4年生からの入塾では、とまどう生徒も多いものです。何らかの事前準備は欠かせません。
(5)小学校高学年(5~6年)
さすがに、この学年になってから、いきなり中学受験を考え始めるご家庭は少ないでしょう。実質的に準備が間に合わないからです。考えられるとすれば以下のようなケースでしょうか。
①小学校でいじめの被害を受け、加害者と同じ地元の公立中学校に進学したくない
②公立中高一貫校なら対策が間に合うかもしれないと考えた
③ご両親とも地方出身で中学受験など考えもしていなかったが、東京の現実に気が付いた
④スポーツで全国レベルの成績が出たため、それに打ち込むために高校受験を回避することになった
⑤地元の公立中学が荒れていて学級崩壊となっていることを知った
⑥勉強が嫌いで全くやらない子なので、高校受験は難しいと考え、今からの準備で入れそうな中高に進学させることにした
どのケースも、私が実際に見聞きしたご家庭であったケースです。
⑥のケースは、小6になってから急に、うちの子はこのまま公立中学に進学させたら大変なことになる、と駆け込み相談があり、私の知っている学校の中から、その子に合う学校をご案内したという状況でした。
夢中になっている趣味の習い事がある、とのことだったので、定員割れレベルの学校の中から、その子の趣味のクラブ活動がさかんであり、面倒見がよく、大学受験も学校が親身に並走してくれそうな、そういう私立校をなんとか探したのです。
幸い、受験はうまくいき、その学校へ進学することができました。
残念ながら、結局勉強についていけずに高校へは進学できなかったそうです。
おそらくは公立中学校よりも基礎的な内容を丁寧に指導してくれていたはずの学校であっても、勉強についていけない生徒というものはいるのです。
こうした生徒は、そもそも中学受験には不向きであると言わざるを得ません。
中学受験のための塾に入るベストのタイミングについては、こちらの記事で詳細に検討しています。
2.中学受験は必須なのか?
職業上の結論からいえば、必須ではありません。しかし、「中学受験のための学びは必須」と考えています。
勉強は大切です。残念ながら小学校の学びだけでは不十分です。やらなければならない時期にきちんと勉強する目標設定として、中学受験の勉強は最適だと考えています。
極論すれば、最終的に中学受験をしなかったとしても、この学びは必須だと思うのです。
ここでは、逆に「中学受験(のための勉強)は不要」である理由を考えてみます。
(1)通える範囲に良い学校がない
さすがに片道1時間が限度でしょう。それを超える通学は、子供の生活時間を圧迫します。しかし、だからといって「勉強は不要」なはずもありません。公立中学進学に向けて、学習習慣をつけたり、必要なことを学ぶのは重要です。
(2)他に目標がある
バレエ・ピアノ・ヴァイオリンといった芸術系、サッカー・野球・新体操・水泳といったスポーツ系、そうした習い事ですでに結果を出している子もいますね。すでに全日本ジュニアの強化選手に選ばれているとか、国内の大会で表彰台に上っているとか、そうした子です。すでに世界に目を向けていますので、算数や理科社会を学ぶより、英語・ロシア語・ポルトガル語・フランス語等を学ぶことが優先されるわけですね。
※ここで私が言っているのは、その世界のトップレベルを目指す決意(&能力&環境)がある子のことです。近所のスポーツ団で毎日サッカーボールを追いかけるのが好きだ、そんなレベルの話ではありません。子供は誰だって好きなことは夢中になります。しかし、そのことが勉強しないことの理由にはならないと思います。
知人のバレエ教室の主宰者の先生がこうおっしゃっていました。
「やっぱり勉強できない子は大成しないのよね。」
なかなか辛辣なお言葉ですが、この教室からは世界で活躍するバレリーナが何名も輩出されていますので、重みがある言葉です。
(3)勉強をさほど必要としない職業を目指す
どんな職業でも勉強は必要だと私は思っています。しかし、世の中にはそこを重要視しない職業もあるのでしょう。
(4)親の資産を継ぐので勉強は不要
コメントは省きます。
(5)勉強に追われない子供時代が大切だと考えている
最近は必ずしもmajorityではなくなってきていると思いますが、そうした価値観のご家庭もあると思います。それに対して私ごときがコメントする立場にはありません。
(6)子供が勉強嫌いである
上記(5)と重なりますね。子供が勉強が嫌いだからやらせない。そうしたご家庭の方針なら、これもまた私ごときがコメントなどできません。
(7)財政上の問題
これは当然重要です。金銭的な無理を押してまで受験に邁進するものでもありません。「うちは子供が4人もいて私立に通わせることは無理だから公立中から公立高校をめざす」というのも、当然の方針だと思います。
ただし、「お金をかけなければ勉強できない」よくそう言われますが、必ずしも真実ではありません。「お金をかけることでいろいろ効率的になる」というのが真相でしょう。
今は、これでけ情報が得やすくなっている時代です。ちょっとネットを検索しただけでも、学ぶための教材やテスト、さらには入試問題やその解説までいくらでも無料で手に入る時代です。本人の意欲と、それをバックアップする両親の意欲があれば、いかなる形であれ学びは継続できると思っています。
(8)目標とする都立(県立)高校がある。
すぐに思いつくのは都立日比谷高校でしょうか。もちろん 都立西高校もいいですね。あるいは神奈川県立翠嵐高校も素敵です。
こうした都立・県立高校を目指す、そうした考えも当然あると思います。
これらの高校には、独自の歴史・校風というものがあり、それに憧れる生徒も多くいます。日比谷高校は明治11年の東京府立一中がルーツです。
また、もしかしてご両親がこれらの高校のご出身であると、わが子にも同じ道を歩ませたい、そう考える方もいるかもしれません。親が自分の出身校に子供を進学させる。とても素敵なことだと思います。「自分の出身校だけには子供を進学させたくない!」こう考えるよりもはるかに良いことは間違いありません。
たしかに私立に比べてと県立高校の大学進学実績は思わしくない場合がほとんどです。しかし高校は大学進学の予備校ではありませんので、それだけを根拠として学校を選ぶべきではないでしょう。
開成高校の先生がおっしゃったと聞きました。開成は中学入試の最難関校としても名をはせていますが、高校入試で筑駒と並ぶ男子最難関校です。
「うち(開成)の合格を蹴って筑駒高校に進学する生徒がいるのは理解できる。しかし、最近うちの合格を蹴って日比谷に進学する生徒がいるのは理解できない!」
高校からの一斉スタートの日比谷高校を選ぶ生徒がいても不思議はないと思います。
(9)公立中学の多様性が重要だと考えている
ご家庭によっては、「いろいろな子がいる公立中学の多様性の中で育つことが重要だ」とお考えの方もいるかもしれません。
これはご家庭の方針ですので、私がどうこう言えることではありません。「多様性」の定義が様々だということでしょう。
〇様々な学力・家庭環境の生徒がいる
〇様々な地域から集まった生徒がいる
どちらも「多様性」には違いありませんが、前者を優先するということなのでしょう。
以上いずれにも該当しないのであれば、中学受験を目標とした学習をぜひしてほしいと思います。
3.教師の本音・・・高校受験の真実
ここから先は、本音を書かせていただきます。すでにお子さんが高校受験を目指して公立中学に通っている、あるいは通おうと思っている方は読まないほうがよいかもしれません。
みなさんは、公立小学校の授業見学をしたことがあるでしょうか? お子さんが小学生なら、年に1回程度はそうした機会があると思います。そこで、どのような感想を抱かれたでしょうか?
私が見せていただいた授業は、耐えがたいものでした。5分で終わるような内容を10倍に薄めた授業内容、不規則発言を繰り返す生徒、立ち歩く生徒、生徒へ全く注意をしない教師。いわゆる学級崩壊をおこしていたわけではありません。新人の教師というわけでもありません。途中で何度も授業に割って入りたくなって困りました。そこで初めて、今まで自分が教えてきた生徒達は、粒ぞろいの子たちだったのだなあ、と気づかされたのです。
中学受験をするご家庭も多くいる落ち着いた学区の小学校ですらこれなら、そうではない小学校はいったいどうなっているのか怖いものがあります。
どうも自分が小学生時代を過ごした小学校とは異なってきているのですね。都内ではありましたが地域的にも時代的にも中学受験をする生徒がほとんどいない小学校でしたが。
背景を考察したのですが、小学校の先生と保護者の関係性が変化しているのが原因ではないかという気がします。以前は、「先生」というだけで尊敬する保護者、そしてその期待に応えようとする教師が多くいたように思います。今はどうでしょうか? 学校の先生を「サービス業」だと勘違いしている保護者が増えているのではないでしょうか? 授業見学をしている周囲の保護者の、近所のコンビニに買い物に行くような服装を見ながらしみじみ考えてしまいました。
高校入試を専門とする塾の教師と話をしていて、違和感を感じることが多くあります。中学受験と異なり、高校入試は必須です。合格できなければ「中卒」になってしまうのです。それなのに、中受を目指す小学生より、あきらかに学習時間が少ないのですね。塾が生徒に与える課題も多くないのです。「いったいどうして?」と聞いた私に、こう教えてくれました。
「僕たちは、中学受験で優秀な層が抜けた後の子たちを相手にしているんですよ。彼らは、そんなに大量の学習にはついてこれません。課題が少ないほうが喜ばれるのです。」
今や、高校入試を実施している中高一貫校は少なくなりました。今はまだ高校募集を継続している学校も、数年後には完全中高一貫教育に舵を切る可能性が高いです。そうなると、必然的に高校入試は公立高校入試を前提として考えざるを得ません。
一度公立高校の入試問題を見てみてください。びっくりするくらい「易しい」です。社会科など、「知っているか知らないか」で勝負がつくような問題が並んでいます。あきらかに中学受験の入試問題のほうが高度な出題で難易度は上です。このレベルの問題をクリアするために中学3年間を過ごすのかと思うと、気の毒になります。おそらく優秀な生徒にとっては足踏みさせられる思いでしょう。そうした生徒たちは、高校進学のその先を見据えた学習を中学生のうちから取り組んでいると思われます。英語なら英検2級レベルの取得を、数学なら数1の範囲の学習を、中学生のうちからやっているのでしょう。最近元気の良い都立トップ校の大学実績が、実は既卒生の成果であることを考えると、それくらいの努力は必要だと思われます。
公立高校受験における内申の重要性とそれに伴う弊害についてはここでは触れません。「先生に気に入られるため」の努力など可哀そうすぎますので。
どのような形であれ、小学生時代の学びは重要です。そして、日本の教育制度の中で過ごす以上、中学入試・高校入試は避けて通れません。そのための学習の目安としては、「中学入試」を目指す学習は非常に有効です。そもそも子供に勉強させない、子供が勉強しないことに理由をつけることが間違っていると思うのです。