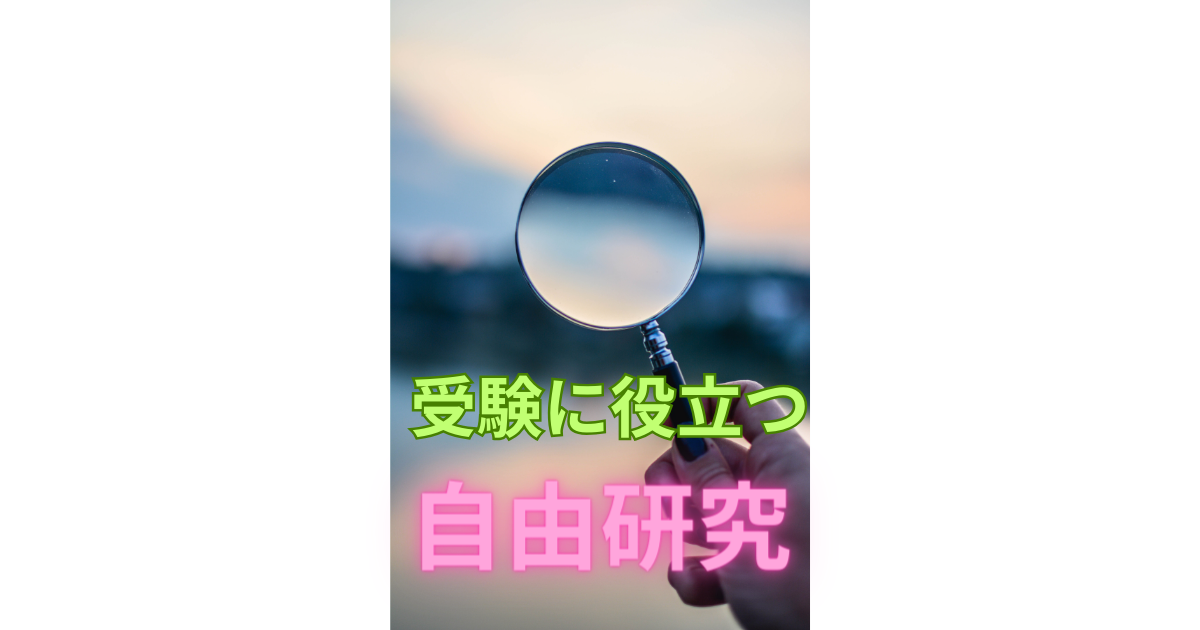
夏休みの宿題として、自由研究を提出させる学校も多いですね。
しかし、中学受験を目指して勉強している生徒にとっては、時間ばかりとられて「正直迷惑!」と考えてしまいがちです。
そもそも塾の夏期講習で時間がありません。
そこで、親がこっそりと手伝う(かわりにやる)などという笑えない話もよく聞きます。
今回は、せっかくやらなくてはならない自由研究なら、中学受験に役立つようにしてしまおう、という虫の良い作戦を考えましょう。
- 1.スーパーマーケット探訪
- 2.コンビニ探訪
- 3.街路樹調査
- 4.ゴミの量定点調査
- 5.歴史人物調べ
- 6.ペーパーブリッジ実験
- 7.生成AIの限界をさぐる実験
- 8.輪軸・滑車の法則が本当か実験で確かめる
- 9.理科の電気回路について、実際に測定して確認する
- 10.地元の福祉施設訪問
- 【自由研究の目的】
1.スーパーマーケット探訪
最もお薦めです。
お薦めポイントその1:時間がかからない。
そうです、近所のスーパーマーケットに行くだけですから、時間はかかりません。半日どころか、2時間もあれば見てまわることはできます。
もちろん、行く時間帯にはご注意ください。夕飯の買い物時等スーパーが混む時間帯は避けるのは常識として、近所のママ友に遭遇するのも避けたいですよね。すいていそうな時間を選んでいきましょう。お店に行った際には、お店の人に一言ことわるのも当然です。「子どもの自由研究があるので、お店の中を少し見てまわっていいですか?」
これで断るような店はありません。
もちろん礼儀として、何か買ってください。
お薦めポイントその2:お金がかからない
遠くまでいきませんので、交通費も入場料もかかりません。まあ買い物をする費用くらいですが、これは必要な買い物をすればよいだけですね。
お薦めポイントその3:社会科学習に直結する
そうです、スーパーマーケットは社会科の学習のネタの宝庫です。野菜コーナーを丹念に調べるだけでも、たちまち自由研究は完成しますし、そのまま社会科の知識として蓄積します。
具体的なネタの例をこの記事に書きました。ぜひごらんください。
実は、このテーマには続きがあります。
中学生になって家族で海外旅行に行く機会があれば、ぜひとも地元のスーパーマーケットを探訪してほしいのです。
日本のスーパーとの共通点や相違点を考えるだけでも面白いですね。
ドイツの、あれは確かケルンのスーパーに行ったときのことです。地元の小さなスーパー、日本でいえば「まいばすけっと」くらいの規模感のスーパーをのぞいてみると、「寿司」コーナーがあるのですね。「こんなところにまで日本食が浸透している!」と感慨深いものがありました。また、ベトナムのハノイのスーパーでは、生きたカエルを売っているのを見かけました。かなり新しいきれいな店で、品揃えはまるでアメリカの近代的なスーパーのようなのですが、その一角で蠢いているのです。カエルたちの未来は考えないことにしました。
2.コンビニ探訪
スーパーに行くのすら時間の余裕がないのなら、近所のコンビニという手もあります。なにせ品揃えも面積も少ないですので、すぐに終わります。
ここで調べるべきポイントはこんなところでしょう。
◆種類別商品点数
◆陳列方法の工夫
◆レジでの工夫
◆買い物以外の利用法
◆客層・どんな買い物をしているのか(あまりじろじろと観察しない)
いわゆるPOSレジの工夫や、公共料金の支払い、あるいは宅配便の扱いなど、単なる商店を超えたサービスを提供していますね。
もちろん注意点はスーパーのときと同様です。
きちんとお店の人にことわること、そして混む時間帯を避けること、さらに何か必ず買うこと。また、他のお客様の迷惑にならないように気をつけましょう。スーパーマーケットよりも狭いですから。
こうしたことの許可を出す権限のある社員(店長)のいる時間帯が望ましいですね。時間帯によってはアルバイトの店員しかいないことも多いですし、おそらくアルバイトの人だと許可を出せないと思いますので。
もし余裕があれば、半径1㎞圏内にあるコンビニのブランド別店舗数など調べると深いですね。同系列のコンビニが近所に並んでいる理由など、実際の入試問題で問われたこともあるのです。
さらに、スーパーマーケットとの比較など行うともっと思考が深まるのですが、おそらくそこまでの時間は費やせないでしょう。
3.街路樹調査
どんな種類の街路樹が選ばれているのか。それは何故なのか。
街路樹は必要なのか、不要なのか。
どちらかといえば理科的な研究につながります。最近話題となった、某中古車チェーン店が店の前の街路樹を伐採した問題がありましたね。店にとっては邪魔だったということでしょう。そこに目を向けると社会問題です。
最近、私の家の近くの住宅街の街路樹が、全て伐採されてしまいました。プラタナスでした。葉が大きく広がり、道にいい感じの木陰を作っていたのです。素敵な住宅街のその道を車で通るのが好きだったのですが、ある日丸裸になってしまいました。
道の雰囲気・街の風景が一変してしまいました。
私の目には、貧相な家が立ち並ぶ(失礼!)貧相な住宅街にしか見えなくなりました。
街路樹の効果って大きいのですね。
いったいなぜ全て伐採してしまったのかはわかりません。
たぶん、大きくなり過ぎたことと、落ち葉の清掃が大変だったことが理由だと思います。
街路樹だけからも、自由研究は成り立つのです。
4.ゴミの量定点調査
自宅で1週間に出るごみの量を定点調査します。
ゴミの種別ごとに家の中にゴミ箱を設置し、毎日重さを計ります。
できれば最低でも10分類はしましょう。
本当は1か月といいたいところですが、それなりに面倒くさいので、最低1週間、できれば10日は続けます。
ゴミの減量が大切だという前に、いったいどれくらいのゴミが家庭から出ているのか、種類ごとに細かく調査してみましょう。
まとめる際はグラフ化し、さらにリサイクルについても調べてみると良いと思います。
環境問題・ゴミ問題についての知見は重要です。
家族の協力は欠かせませんが、小学生が一人で取り組める内容である点がお勧めです。
5.歴史人物調べ
例えば、徳川家康~慶喜まで、15代にわたる将軍について詳細に調べてまとめてみましょう。
おそらく、系図をまとめるだけでも一苦労です。複雑怪奇ですので。しかし調べがいはあります。
大きな模造紙一面に詳細な系図を作り、そこに15人の将軍の写真などを並べ、さらに業績や人間関係などまとめるというのはどうでしょう。
なかなかの大作&労作が完成すると思います。
しかも、江戸時代の理解に非常に役立ちます。
まさに一石二鳥です。
もちろん、徳川以外にも、たとえば足利将軍15代でもかまいません。もっとも細かすぎて、中学入試レベルではなくなります。
同じ理由で、奥州藤原氏もやめたほうがよさそうです。前九年・後三年の役は複雑すぎて、しかも細かすぎて中学入試レベルを超えますので。
6.ペーパーブリッジ実験
ヒントはこれです。
昔、テレビの子供向け科学番組でも見たことがあります。
自分で条件を決め、工夫し、精密に測定します。
どのような構造が最も重量に耐えられるのか。
シンプルですが奥深い実験です。
さすがにベクトルの知識がないので構造計算めいたことすらできませんが、直観でわかることが大切です。
てこやてんびんの理解につながります。
実は大人でも盛り上がります。
7.生成AIの限界をさぐる実験
chatGPTが公開されていますね。
他のAIでもかまいません。
生成AIに様々な質問をして、答を分析しましょう。
どういう質問なら適切な答が返ってくるのか。
どういう質問が苦手なのか。
得意・不得意を探るのです。
実は、昨年から今年にかけて、生成AIを取り上げた入試問題が増えています。おもに社会科と国語です。
今、教育現場では、この生成AIとどう向き合うのか、悩んでいる最中です。
おそらく本音としては完全拒絶したい先生が多いと思います。しかし、時代の流れとしては無視し続けるわけにはいかない。それでは、どうやったら教育に有効活用できるのか。こうした試行錯誤をしている最中なのですね。
だからこそ、生成AIの問題点を記述させたり、あるいは歌人と生成AIの話題をとりあげた問題が出たり。
一度徹底的に探ってみるのも有効だと思うのです。
少なくとも、論理的思考力の養成には役立ちます。
8.輪軸・滑車の法則が本当か実験で確かめる
理科で出てきますね。輪軸と滑車の問題が。
お子さんは得意でしょうか?
けっこう面倒くさい計算問題が理科では出題されています。
しかも、ここまで細かい実験など小学校ではやりませんし、もちろん塾でもやりません。
完全に思考実験だけなのです。
だったらいっそのこと、ほんとうに実験してみませんか?
必要な材料は、ホームセンターに行けば簡単に手に入ります。
あらゆるバリエーションを、実際に手を動かして測定してみましょう。
ここで身に着いた感覚は、確実に入試問題を解くのに役立ちます。
しかも、知識として覚えさせられるのではなく、自分の手と目で確かめようとする姿勢、まさに科学にとって最重要な姿勢です。
9.理科の電気回路について、実際に測定して確認する
電気回路の問題は得意ですか?
豆電球レベルならともかく、電気抵抗・電流・電圧などがからんでくる問題になると、正直いって中学生の理科の範囲になりますので、小学生にとってはなかなか難しくなるでしょう。
しかも、小学生の受験理科指導では、きちんとした公式を教えずに、変な簡略化した計算方法を教える塾・先生も多く(大半)、かえって混乱をまねきます。
それならいっそのこと、オームの法則を実測して確認する勢いで、きちんとした電気回路の知識を体得させてしまうのはいかがでしょうか。
用意するのは、基本的な電気回路の部品・・・電池・銅線・LED・豆電球・スイッチなどですが、さらにマルチメーターも必要です。
デジタルマルチメーターは、安いものなら1000円台からネットで購入可能です。
小学校の理科の実験ではやりませんし、塾でもやりません。中学校も、きちんとした実験をやらないところも多そうです。
ここで身に着いた知識は、中学入試ばかりか、中学校の理科の理解にも役立つのです。
10.地元の福祉施設訪問
介護施設・デイサービス施設・こども食堂など、多種多様な福祉関連の施設が近所にもあると思います。そこを訪問するのです。
訪問する前にはもちろん事前の連絡が必要です。どんな意図なのか、聞きたい内容は何なのかをあらかじめ整理して、先方に連絡しておきます。そのうえで訪問しましょう。
貧困家庭の問題や少子高齢化等、社会問題については中学入試でも深いレベルまで出題されています。本やネットで見るだけではなく、実際に足を運び、福祉に携わる人のお話を直接聞くことはとても良いことだと思います。
そして、調査の基本的な手法も身に付きますね。
〇調査の意図を明確にする
〇調査したい内容を整理する
〇上記2点をあらかじめ伝えておく
〇訪問し、整理しておいた項目にそって話をうかがう
〇さらに自分が事前に気が付かなかった内容に注目し詳細をうかがう
〇事後、プレゼンできるように調査内容を整理しまとめる
〇プレゼン内容を、協力してくださった相手にも送る
こうした手法を実体験できますね。
【自由研究の目的】
おそらく小学校で夏休みに自由研究を課題とするのは、以下の2種類の研究を期待しているのだと思います。
(1)調査
上述した福祉施設の調査のように、調査研究の基本的な流れを体験し、まとめてもらうことを目的としているのでしょう。また、コンビニ探訪のように、調査から新たな疑問点がうかび、それを考察するという流れも作れます。
(2)実験
テーマを決め、仮説を立て、実験で検証し、結果を考察する。科学の基本的な手法を学ばせることが目的です。
そう考えると、避けるべきなのはどんな自由研究なのかも見えてきます。
◆手間暇をかけたことだけが評価されるようなもの
例えば、「多摩川を歩いて源流まで遡ってみた」とか、「昆虫採集100種類にチャレンジした」といったものでしょうか。
その労力、それも並大抵でない労力には脱帽しますが、ただそれだけです。「研究」要素がないからです。
今回は、以下の3条件を考慮してみました。
1.遠くへ行かなくてもできる
2.時間をかけなくてもできる
3.お金をかけなくてもできる
何せ受験生は忙しいのです。時間がありません。
近場で時間もお金もかけずに、しかも中学受験に役立つような、そんなアイデアを考えてみたのです。
他にもいくらでもあると思います。
どうか、せっかくの夏休みの自由研究ですから、転んでもただでは起きないというか、入試にも役立つことを考えてみてはいかがでしょうか。