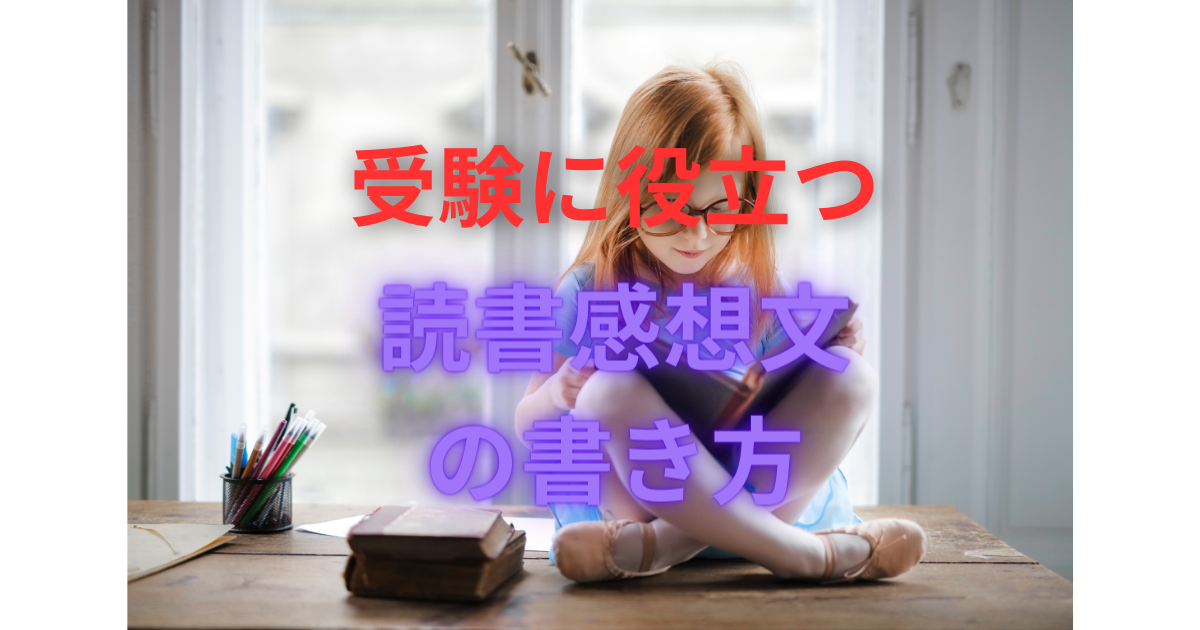
まだ少し気が早いですが
小学校の夏休みの宿題といえば、読書感想文ですね。
ところでお子さんは読書感想文が好きですか?
私の経験上、好きな生徒はいませんでした。
でも、どうしても書く必要があるのなら、せめて中学受験に役立たせよう、という、今回は姑息な作戦を考察します。
1.そもそもなぜ子どもたちは読書感想文が嫌いなのか?
それは簡単です。
大人だって嫌いだからです。
みなさんは、小学生時代に読書感想文を書くのがお好きでしたでしょうか?
YES、と大きくうなずいた方は、この先は読む必要がありません。
その気持ちをお子さんに伝授してください。
NO、と大きく首を振った方のために、この記事を書いています。
何を隠そう、私も大嫌いだったからです。
そもそも、読書って、楽しいからするものですよね?
とくに小学生時代の読書はそうあってほしいものです。
時間のたつのも忘れて夢中でページをめくる。残りページが少なくなってくるのがせつない。読み終わった後、本を閉じるのも忘れてしばらくぼんやりする。
小学生の時にそうした幸せな体験をすれば、きっと中高生になっても読書が心を豊かにする大きな楽しみとなると思います。
それなのに、感想文?
もう、意味がわかりません。
「ああ、おもしろかった。」
「なんだか哀しい気持ちになった。」
「この作者の本、他にもないのかな?」
「もう一回最初から読もう!」
これでいいと思うのです。
読書というのは、きわめて主観的な行為です。同じ本でも、人によって受け止め方は様々です。無理やり感想を言語化する必要などないのです。
と、こんなことを言っていては、いつまでたっても「読書感想文の攻略法」にたどり着けませんね。
どうせ嫌々書かされるのであれば、せめて中学受験に役立たせるにはどうしたらいいか、そんな観点から攻めてみたいと思います。
2.どの本を選ぶべきか?
学校から指定されたのなら、その本を読むしかありません。
もし何冊かの候補が挙げられていて、その中から選ぶのなら、こんな本を選んでみましょう。
これは、自分で自由に本を選ぶ場合も同様です。
(1)主人公が小6~中2くらいの物語
物語ですから、もちろん主人公がいます。そこで、主人公が自分と同年代か少し上の年代の少年・少女であるものを選びましょう。
そのほうが感情移入しやすいので読みやすいからです。
読書は、あまりにも自分とかけ離れた年代の主人公のものだと、全く没入できませんし、読んでいてもおもしろくはないでしょう。
(2)自分と同性の主人公の物語
主人公はやはり自分と同性が望ましいですね。男子が女子の気持ちを、女子が男子の気持ちを知る目的の読書もありますが、どうせなら同性のほうが読みやすいことは間違いありません。
(3)時代設定は現代のもの
戦争中であったり、あるいはもっと昔の物語は、やはりどうしても読みにくく感じます。読みにくいということは、感想文も書きにくいということです。なるべく現代が舞台のものがよいですね。
(4)舞台は日本
海外の小説にも読むべきものはたくさんありますが、ここでは日本限定で読むことをお勧めします。物語世界に入るのに時間がかからずにすむからです。また、翻訳によってもかなり違います。残念ながらあまり評判のよくない翻訳物もありますので。
(5)主人公は問題を抱えている
全てが順風満帆、陽気で誰からも好かれ、家族仲もよい。友人たちから頼られる存在。そんな主人公の小説、読む気がしますか?
やはりここは、なにかの問題を抱えてくれていないと物語が始まりません。
・両親が離婚している(しそうである)
・いじめにあっている・いじめる側・いじめを目撃してしまった
・転校してきたばかり・これから転校するところ
・盗みの濡れ衣をきせられている
(6)主人公が問題を抱えている人物と出会った
・海外から移住してきた家族と出会う
・一人暮らしの老人と知り合う
・閉店直前の店の人と出会う
・転校生と仲良くなる
・皆に嫌われている同級生と交流する
主人公が、仲の良い同級生や家族にだけ囲まれて、幸せな日々を送っていて、周囲には不幸な人物が一人もいない。そんな状態では物語が全く発展しません。
やはり、他人の心の痛みと出会い、その痛みをなんとか理解しようともがくことで、物語は進むものです。
(7)主人公が成長する物語
かかえている問題が解決し、主人公が大きく成長する。よくある話ですね。またそこまで成長しないとしても、前へ向かって少し歩み出す、そんな物語もあります。
(8)今年・去年あたりに大きく話題になった本
話題になったということは、それだけ多くの人に支持されたということですね。そして話題になるということは、現代的なテーマを扱っている可能性も高いです。そうした本をぜひ読んでみましょう。
(9)全く想像もつかないような別の世界がテーマの話
いっそのこと、子どもには想像もつかないような世界を描いた物語というもの良いと思います。もちろん異世界物のことではありません。
たとえば、こんな本のことです。
『線は、僕を描く』砥上裕將
2019年に出版され、それなりに話題となった本です。2022年に映画化されましたので、そちらのほうでご存じの方もいるかもしれません。
実は、中学入試にも出題されています。
江戸川取手中、場東邦中、市川中、三輪田中あたりで出題されていたと思います。
内容は、今までお勧めしてきたものとは異なります。
大学生の主人公が水墨画に魅了され成長していく、そんなお話です。
水墨画の世界など、小学生には無縁です。だからこそ、おもしろいですし、読む価値があると思うのです。
同系統の本としては、調律師の青年を主人公とした『羊と鋼の森』や、ピアニストを主人公とした『蜜蜂と遠雷』もいいですね。どちらも入試に何度も出題されています。
(10)課題図書から選んでみる
「全国学校図書館協議会」が主催する「青少年読書感想文全国コンクール」というものがあります。学校単位で応募する場合も多いイベントです。
今年の課題図書はこのようになっています。
【小学校高学年の部】
「ぼくはうそをついた」 西村すぐり作
あの人を救いたくて。原爆で亡くなった息子のフリをした。少年のまなざしを通して、平和への祈りと希望を描いた物語
◆選定理由:タイトルから、読者は「なぜ」と思いを巡らせて読み進めていく中で、一人ひとりの判断や行動には理由があることなどを感じ取ったり、自分の日常と生活を関連付けて考えたりすることができる。
「海よ惹かれ!:3.11被災者を励ました学校新聞」 田沢五月 作
東日本大震災の避難所の小学校で子どもたちが取り組んだこととは…。子どもたちの思いをつぶさに伝える感動のノンフィクション。
◆選定理由:読みやすい文章で、新聞の役割と紙面構成、記事の書き方がわかる構成で、ノンフィクションとして優れている。震災当時の子どもたちの活動や地域の絆の大切さが描かれている。
【中学校の部】
「ノクツドウライオウ:靴ノ往来堂」 佐藤まどか 著
祖父の作った靴を持つ人たちにおきた、人生を変えるほどの変化。それは進路に迷う夏希の心を大きく揺さぶる。さわやかな青春物語。
◆選定理由:靴づくりの細かなところまで描かれており、物作りの魅力にどんどん引き込まれていく作品。大切に扱えば長く使えるものとの出会いは、気づかないだけで身近にあることがわかる。
3人の中学生が古い井戸を見つけた。願いが叶うという伝説の井戸が、町の人たちに次々と奇跡を起こす!?愛と希望があふれる物語。
◆選定理由:
登場人物が多く、連続ドラマになりそうな多彩なエピソードで構成され、飽きずにぐいぐい読める。ちょっとした気づきや優しさが、人の助けになるかもしれないと思わせてくれる。
「アフリカで、バッグの会社はじめました:寄り道多め仲本千津の進んできた道」 江口絵理 著
アフリカの貧困問題を解決し、女性を輝かせたい――自分の本当の夢を追いつづけた仲本千津さんの“進路決定”ドキュメンタリー。
◆選定理由:大変わかりやすく書かれ、言葉の選び方、ページ数など伝わることを大切にしている編集、読後に明るい未来を思い描ける内容。表紙に描かれたバッグの写真も印象的。
公式サイトから、5冊ほどをそのまま引用してみました。
なかなか自前で探すことのできない本が挙げられていてとても助かりますね。
何を読んでいいのかわからない場合は、この中から選ぶというものありです。
さて、そろそろお気づきかと思います。
ここで考えているのは、「中学入試に出そうな」本なのです。
正直言って、入試の国語の試験問題の文章を的中させるのはなかなか困難です。今年1年で出版された本を中心に、いかにも出そうな本というのはある程度予想がつきます。
しかし、その本の中でどの部分が問題に使われるのかまではなかなか予想が難しい。まして、その文章を、いったいどの学校が出題するのかはまでは予測不可能です。
よく塾が、「この文章が的中!」とやっているのは、いくつもの文章をテキストに使ったり生徒に話していたら、どこかの学校で出題された! ということにすぎません。
生徒の受験する学校が延100校(複数回受験も含む)にわたれば、どこかの学校で出題がヒットすることもあるでしょう。
とはいえ、こういった種類の物語を読むことは無駄になるはずもありません。
もしかして当たったらラッキーですし、当たらないとしても読解力向上の良い材料となるからです。
3.どう書くか?
(1)王道
読書感想文には王道の書き方があります。
1.どうしてその本を選んだか・・・本の紹介・あらすじの紹介
2.感動したところ・印象に残った場面・心を動かされたところ
3.自分なりに考えたこと・読書前後で自分がどう変わったか
この3ポイントを基本構成として、あとは膨らませていくのですね。
ちょっとネットを検索するだけで、読書感想文のテンプレートまでいくつも見つかります。
「このテンプレートに入れるだけで、60分で完成!」などとなっていますね。
いっそのことこれを利用して、1時間で終わらせるというのも悪くないかもしれません。そうすれば残りの時間を有効に(つまり受験勉強に)使えるというものです。
それも良いような気もしますが、ここではそれは邪道として、あくまでも読書感想文を中学受験に役立てる方向で考えましょう。
(2)物語の舞台を整理する
ホワイトボードに、物語の舞台を書き出します。
どの国のどの町の話なのか、舞台は学校なのか、あるいは家庭なのか。さらに時代はいつなのか、季節は、そして時間は。
このように綿密に物語の舞台を整理していきます。
とくに時間帯や季節など、はっきりと書いていないものもありますが、文章中からヒントを探しだし推理していきます。
(3)登場人物を整理する
物語に登場する人物を全て書き出します。
それぞれのプロフィールについて、わかるかぎり書き出します。年齢・性別・性格・家庭環境等ですね。
(4)登場人物どうしの人間関係を整理する
友人なのか。友人だとしたら親しいのか、仲が悪いのか。細かく把握していきます。
ここでは思い込みは排除してください。文章中からはっきりと推理できることだけ書いていきます。その際に有効なのは、登場人物のセリフです。そこには彼らの人間関係を知る大きな手掛かりがあるからです。
(5)物語の場面転換に注目する
場所や時間が動いた部分に注目しましょう。場所が変わり、時間が移っていれば、その間に何等かの変化が生じているはずだからです。物語が大きく動きだすところに注目しましょう。
(6)自分の好きな登場人物・嫌いな登場人物を選ぶ
どの登場人物が好きなのか、その理由は何か。あるいはどうして嫌いなのか、その理由は何か。こうして自分なりの感想をまとめていきます。もちろん主観でいいのです。ただしその理由を明確にしなくてはいけません。
「僕は太郎が嫌いだ。なぜなら、太郎は内向的な性格ではっきりと意見を口にしないから、その結果かえって周囲の人を傷つけているからだ。さらに、まわりを傷つけたことに気づいていない太郎のデリカシーの無さも嫌いな部分だ。」
こんなぐあいでしょうか。
(7)自分に置き換えてみる
もし自分が太郎だったら? このように考えてみることも有効な読解方法の一つです。そうすることで、太郎の行動の背景にあるものが見えてくるかもしれません。
(8)この本、人に薦める?
薦めたいならその理由を、薦めたくないのならその理由を。こうしてきちんと理由まで考えることで、ただの主観が客観性を持ってくる、つまり説得力が増してきます。
4.受験にどう役立つのか
ここまですすめれば、読書感想文はほぼ完成しています。
しかも、文章の読解まで完璧にできました。
そうです。どうせ読書感想文を書くのなら、いっそのこと徹底的な読解の練習にしてしまえばいいのです。
普段の問題演習では、長い物語文のほんの一部をとり出して読解しています。
この読解がきちんとできれば、問題は解けます。
記号選択で間違えることもありませんし、記述問題も楽勝でしょう。
今回は、もっと長い文章、つまり物語文全体を読解の材料とすることで、読解力を徹底的に鍛えようという試みでした。
正直いって、この読み方は楽しくないですね。
そこで、せめて1回目は、単に楽しんで読ませてあげてください。
そしてそのあとに、ホワイトボードを前にして、親子で協力して読解をしていくことにしましょう。
もちろん前提としては、親もこの本を読んでおく必要があります。
もし親の解釈と子どもの解釈が異なる部分があったとすると、そこはまさに読解させたい部分、つまりなぜ解釈が異なったのかを十分に考察すべき箇所だということです。
さらに、そうした部分が入試でも狙われる部分でもあるのですね。
これが、読書感想文を中学受験に役立たせる方法です。