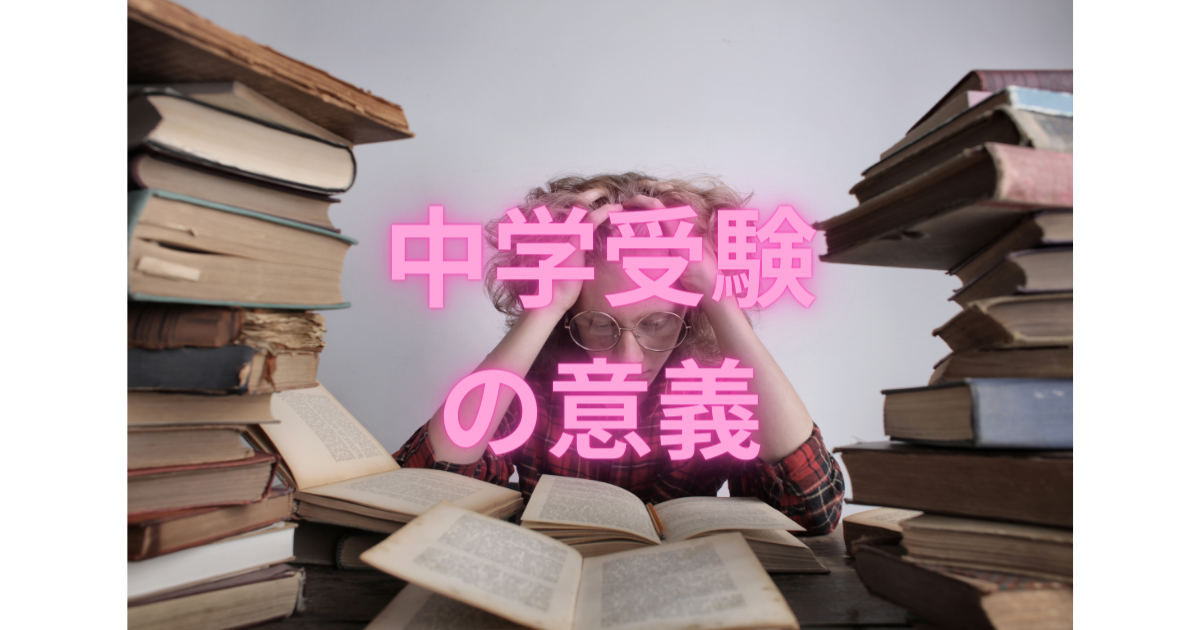
このテーマについては、過去に何度も書いてきました。
書いてきた、と思っていたのですが、いま改めて自分の書いた記事を振り返ってみると、あちらこちらで書いてはいるものの、まとまりがなかったですね。
そこで、今回は正面からこの話題に切り込んでみることにします。
※私は中学受験が主戦場です。どうしても中受肯定派であることはあらかじめお断りしておきます。
中学受験をすることのメリット
ある調査によると、2023年の入試における首都圏の受験人数は、私立+国立を合計すると5万2000人~5万5000人、受験率は17.9~18.6% だそうです。
これは首都圏全体の数値ですので、東京の23区でも受験率の高い区では私立中学進学率ですら40%を軽く上回るそうです。
実際には、受験率の高いとされる小学校では8割ほどの生徒が中学受験をするといわれています。
私の知人にも小学校の先生をされている方が複数いらっしゃるのですが、「2月1日に学校に行くと、教室には3人しか生徒が座っていなかった」などと言う話をされていました。
ここまで中学受験が一般化している状況の中で、今更「中学受験はする必要があるのか?」と問う方も少なくなったと思います。
でも、だからこそ今一度じっくりと考えてみる必要があると思うのです。
ほんとうは、子供の教育についてメリット・デメリットで語るのは間違っていると思っています。なぜなら、教育だけが、親が子供に与えてあげられる最大のギフトだからです。我が子の教育に関心がなく学校任せの親というのは、私にはとても信じられません。
しかし、教育の方法は様々です。
そこで、あえて中学受験をすることのメリットについて考えてみることにしましょう。
6年間の環境
これこそが、最大のメリットであり、唯一ともいえるメリットです。
12歳~18歳という、自我が確立していく多感な時期に、どういった友人や先生に囲まれてどのように過ごすのか。
私の周囲は中学受験経験者ばかりです。兄弟・親戚等、みな中学受験をして私立(国立)中高に進学しました。友人もそうした人間ばかりです。
さらに私はこんな仕事をしていますので、今までに多くの(数千人!)生徒の私立(国立)中学への進学をサポートしてきました。
だからこそ、私立(国立)中高一貫校のメリットについては語る資格があると思うのです。
その最大のメリットが、6年間を過ごす環境にあるのです。
物理的な環境
公立中学にも、とてもめぐまれた施設・環境の学校もありますし、私立といえども狭い校地・古い校舎の学校も多くあります。
したがってこれはあくまでも一般論ですが、私立のほうが校舎や設備が恵まれた学校が多いですね。
神奈川の栄光の11.1万㎢は格別としても、桐朋7.4万㎢、浅野5.68万㎢、武蔵3万㎢といったあたりが恵まれた校地ですね。
女子では、浦和明の星3万㎢、鴎友4万㎢あたりが広いですね。ところで桜蔭は0.7万㎢と狭くグラウンドもありませんが、かといってこの学校を「ダメだ」と判断する人はいないと思います。
山脇学園も、短大の敷地をそのまま中高が使用していますので、面積にそうとうゆとりがあります。1.6万㎢くらいだと思います(非公表)。なんといっても山脇は赤坂に立地していますからね。この場所でこの敷地は羨ましいかぎりです。
ただし、これらを公立中学と比較するのはずるいですね。中高一貫校ですので、中学よりは広いのは当たり前だからです。
他にも、学校によっては、多摩川の河川敷に広いグラウンドを所有していたり、箱根や軽井沢に別荘(合宿所)を所有していたりすることも珍しくはありません。
※設備だけにとらわれない
ライブラリー・カフェテリア・実験室など、「目立つ」施設を充実させている私立は多くみられます。
ただし、この施設の充実に関しては、生徒集めに利するための手っ取り早い方策であることも考えましょう。
ある私立校を見せていただいたときのこと。案内してくださった先生が自慢の部屋を見せてくれました。3Dプリンターがずらりと並んでいるのです。これを授業に活用しているのか。凄いなあ、と感心させられたものです。
さて、先日その学校出身の大学生になった生徒と話をしていると、たまたま3Dプリンターの話になりました。「あ、あれ。全く授業で使っていないですよ。部活でもめったに使ってないんじゃないかなあ。あ、文化祭のときだけ、見せてました。」とのこと。
まあ、そんなものですよね。
人間関係=環境
中学受験という関門(しかもとても困難な)を突破して入学してきた生徒は、皆高い学力をもっており、また努力の価値を体現した者たちです。そうした生徒を相手にする先生方もまた、高い水準の授業を展開できる方ばかりです。そうした環境に身を置いて学ぶことがいかに学びの喜びに満ちていることか。
そこでは学びにブレーキをかける必要もありません。
興味のわくテーマがあれば、どんどん深堀りしてもかまわないのです。むしろ、よく学ぶものが崇敬される環境があります。
「がり勉」という言葉がありますね。
ひたすらに勉強にとりくむ学生に対して「否定的」に使われる言葉です。
私はそこに違和感を覚えます。「がり勉」のどこが悪いのでしょうか? 中高6年間は、ただひたすらに勉強に打ち込む時期に他なりません。勉強をすべき時にやらずして、いったいいつ勉強するのだろうかと思います。
勉強以外の「学び」についても充実した環境が得られます。
例えばクラブ活動についても、中学と高校で分断されませんので、じっくりと5年間(5年半)は取り組むことになります。
留学する生徒も多くいます。
中学3年か、高校1年あたりが留学のベストタイミングです。ここで1年間の交換留学を経験することもまた可能な環境です。学校によっては多くの海外の学校と姉妹校の提携をしてチャンスを広げているところもありますし、もちろんそんなものがなくても学校の先生に相談しながら自分で留学先を見つける生徒も多くいます。
私の教え子で男子最難関校の一つに進学した生徒は、自分で奨学金つきの無料で留学できる制度を探し、中学~高校にかけて世界各地に短期留学を繰り返していました。そのままアメリカのアイビーリーグあたりに進学するのかと思いきや、東大に進みました。
本人曰く、「海外はもう飽きたから、これからは日本に腰を落ち着けてじっくり学ぶ」のだそう。生意気ですが、そんな生徒が普通にいるのもまた中高一貫校ならではだと思います。
こうした話をすると、「中高一貫校にも落ちこぼれはいる」と反論されますが、それは当たり前です。(残念ながら私には落ちこぼれについて語る資格も十分にあります)
生涯における最良の友が得られるのはいつの時期なのか、それは様々だと思います。幼稚園から小学校が一緒だった幼馴染かもしれませんし、大学で飲み明かした友かもしれません。でも、中高6年間が最も大切な時期ではないでしょうか。
学校に対する気持ち
公立中学の場合、その学校は「目標として努力して入学した」学校ではありません。しかし私立(国立)中学の場合は、「そこを目標として努力を重ねた結果入学が許された」学校です。生徒の学校に対する気持ちに大きな違いがあることはおわかりいたけるでしょう。
その気持ちが強く、卒業した後もつながり続けるような校風の学校もあれば、卒業と同時につながりがなくなるさっぱりとした学校もあります。
そういえば、岸田文雄首相を支えたのは、「永霞会(永田町・霞が関開成会)」という開成OBたちだそうですね。支えたというよりは、岸田首相が率先して会長となって立ち上げたのが永霞会です。永霞会決起集会には、600人以上の開成出身の政治家・官僚が集まったそうですね。
そんなつながりなどなくとも、「価値観が共有される安心感」のようなものがあると聞きます。それは私にもよくわかります。
私の知人に、都内有名女子校(お嬢様学校系)出身で広告業界でバリバリと仕事をされている女性がいます。本人曰く、学校では相当の問題児だったそうですが、今でも当時の担任の先生とは仲良くされているそうで、母校の校長となったその先生を訪ねて校長室に遊びにいったりしているそうです。
思春期の6年間を過ごした学校と、強くはなくとも何となくつながっているような感覚があるのも悪くはないと思います。
高校受験で足踏みをしなくてよい
高校受験のメリットをあげる方も多くいます。
・高校受験があるから中学3年間をだらけずにすごせる
・中高一貫校に高校から入った者のほうが成績が良い
どちらも真実なのかもしれません。
しかし、まずは高校入試の問題を見てみてください。
びっくりするほどの基本問題が並んでいます。
もちろん、基本は大切です。とはいえ、この問題をクリアするためだけに、3年間も足踏みさせられるのはつらいだろうなあ、と思わざるを得ません。
私立であれば、進度が早くないといわれる学校ですら、中2で中3までの内容は終わり、中3からは高1の内容に入るのが普通です。特別に急いでいるわけではありません。変なブレーキをかけなければ、優秀な生徒たちならそれくらいの進度が適切なのです。
内申点を気にする必要がない
もちろん、中高一貫校生にとっても学校の学習が第一なのは当然です。内申点も大切です。
しかし、高校受験における内申点の重要性とは比べ物になりません。
都立高校の入試についてとりあげましょう。
詳しくは、東京都教育委員会のHPの中にある、「都立高校の入試制度について」を参照してください。
〇英語・数学・国語・理科・社会の評定点→そのまま合算・・・①
〇音楽・美術・保体・技家の評定点 →2倍して合算・・・②
①+② (65点満点)を300点満点に換算し、学力試験700点満点と合わせる
例えば、次のような評定のAさんが、学力検査が5教科、学力検査の得点と調査書点の比率が7:3の学校を受検する場合
国:5、数:3、 英:5、 社:4、理:3、
音:3、美:4、保体5,技術:3
(5+3+5+4+3)×1+(3+4+5+3)×2=50点
50点×300点÷65点=230点 ※小数点以下切り捨て
700点換算の学力試験を受ける前に、すでに230点の得点が得られる(あるいは得られない!)ことになります。生徒たちが内申点を上げることに必死になるのは当然です。
この内申点というのが曲者です。
定期テストの結果のみがダイレクトに反映するのならわかりやすいのですが、そうではないため不透明さがぬぐえないのです。
内申点の評価基準は以下のようになっています。
「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力など」「学びに向かう力、人間性など」
担当の先生の主観に基づく基準が多いのですね。
そのため、巷には「内申点を上げるコツ」といった情報があふれています。ちょっと検索してみると、このようなものがありました。
〇ノートは丁寧にまとめておくこと
〇「自分の意見」を必ずレポートには盛り込むこと
〇実技には熱心に取り組む様子をアピールし、あきらめないこと
〇先生の話を聞くときには、熱心に頷きながら聞くこと
〇クラスメイトへのアドバイスを目立つようにすること
〇積極的に先生に質問をすること
ううむ。どれも大切です。大切には違いないのですが、何か違和感を感じるのは私だけでしょうか。
さらにこのようなアドバイスまでありました。
〇生徒会活動には必ず立候補し積極的に参加すること
〇担任が顧問のクラブ活動を選ぶこと
これは内申点には直接関係しないとも書かれてありましたが。
このように不透明でわかりにくい高校入試と比べて、中学入試は実にすっきりとしたものです。
入試本番の得点。これのみで合否が決まります。
充実した小学校生活を送れる
こう書くと、それは逆では? と思われるかもしれません。
では逆に質問します。充実した小学校生活ってどんな生活ですか?
野球やサッカー、バレエや新体操、ピアノやヴァイオリン、何でもいいですが、すでに夢中になって打ち込んでいる何か、将来も続けるはずのものがある場合はよいのです。でも、ほとんどの小学生は、そこまで打ち込む「何か」をもってはいません。それなら、「勉強」に打ち込むのはどうでしょうか。
中学受験というのは、とてもわかりやすい目標設定です。たとえ不合格になって公立中学に進学することになったとしても、この勉強の経験は大きな糧となります。もちろん合格すれば、さらに大きな褒美が待っているのです。
自分で努力し、その結果を自分で受け止める。
わずか12歳でそんな体験ができるのは、中学受験をおいては他にはないと思います。
これこそが充実した小学校生活だと私は考えます。
選択肢が多い
高校受験だと、都立・県立高校受験がメインとなります。
私立中高一貫校で高校募集をしているところが非常に少ない(ほとんどない)からです。従来は高校募集をしていた学校も、続々と打ち切り、6年一貫教育へと切り替えてきています。
すると、高校受験の選択肢は以下のようになるのです。
◆都立・県立高校
◆難関私立中高一貫校・・・激戦!
◆大学付属高校
◆不人気私立高校
中学受験することのデメリット
中学受験にデメリットなどないと思いますが、やはりいくつかのデメリットを指摘する方はいます。
生徒に多様性がない?
勉強に熱心に取り組む生徒も勉強に後ろ向きな生徒も、さまざまな生徒が公立中学校には通っています。それを多様性ということもできるでしょう。しかし、私立(国立)中学には、広い地域から生徒が通ってきます。これもまた多様性ということができますね。
公立中学については、年度によって、地域によって、担当教師の力量によって、たまたまとても良いクラス運営ができていることもあれば、学級崩壊となっている場合もあります。これは多様性とはいいません。いわゆる「やんちゃ」な生徒との交流も大切な経験だと考える方にとっては、私立(国立)中学はぬるま湯に思えるのかもしれませんね。私はそんな交流に価値を見出せませんが。
のびのびとした小学生時代を送れない
地方出身のお父様と面談をしているとよく出る話です。
「私らの子供のころは、外で真っ黒になって遊んでいたものですよ。それが今の子供たちは、青白い顔をして塾に通っていて。何かおかしいですよね?」
地域と時代が異なるのです。
とくに都心部においては、小学校が終わると、多くの生徒が塾・習い事などに向かいます。近所の公園で暗くなるまで遊んでいる子が少数派の時代です。
しかも、遊びといっても、数人の男子生徒が固まってゲームをやっている。そういう時代でもあります。
地域とのつながりが薄くなる
これは明らかなデメリットです。
小学校・中学校、もしかして高校まで地元に通っていると、友人ネットワークが地元に張り巡らされます。こうしたご近所ネットワークがどうしても築けないのも、私立(国立)中高一貫校に通うことのデメリットといえるでしょう。
教え子に聞いたところ、成人式には、振袖を着て写真はとるけど、役所主宰の「成人を祝う会」はパスしたと言っていました。出席しても知り合いがいないからだそうです。公立中学に進学した子たちが学校単位で集まっているので居場所はないといっていました。
それも少々寂しい話だとは思います。
もっともそのかわりに、中高の同窓会が主催して都心のホテルで成人のパーティーが開かれたと言っていました。それならいいですね。
通学時間がかかる
それはそうですね。歩いて行ける範囲に進学したい私立(国立)中学校がある恵まれた環境の方は少ないでしょう。(子供の進学を期に千代田区一番町に引っ越した方の話を聞きました。うらやましすぎます)
混雑した電車・バスをつかった6年間の通学。仕方のないこととはいえ、なるべくなら自宅から近い学校を選ぶしか対策はありません。
周囲から色眼鏡で見られる
別にデメリットというほどでもありませんが、〇〇中高に通っている(卒業している)という、ある種のフィルターがかかって見られることもあるかもしれません。
私の知人のいわゆるお嬢様学校(昔から良家の子女(死語!)が通うとされた伝統校)出身の方は、「あら、お嬢様なのね」とみられることが多いそうです。本人は全くお嬢様ではありません。もっとも本人は少しうれしそうでした。
開成や桜蔭出身と聞くと、みなさんはどのようなイメージをもたれますか?
開成・桜蔭→東大、医学部 というと違和感はないですね。でも、いわゆるFランとよばれるような学校に進学する生徒ももちろん存在します。
「開成(桜蔭)なのに〇〇大学なんて」と言われるのは嫌なものでしょうね。
まあそんなものは気にしなければいいだけの話です。
お金がかかる
これはもうどうしようもない現実です。
私立中高にはお金がかかります。
教育費が捻出できない事情なら、もう公立・私立のメリット・デメリットなんて話はどうでもいいですね。
与えられた環境で最大限の努力をするだけです。
そうした道もまた、子どもの成長に大きくつながると思っています。
※ただし、お金をかけなくても受験勉強は可能です。また、都内であれば高校無償化の恩恵も存在します。あるいは公立中高一貫校を目指すという方向もあるでしょう。
大学受験に有利かどうかはどうでもよい
中高一貫校を選ぶときに、大学の合格(進学)実績を気にされる方は多いですね。
もちろん、それも学校のレベルや指導を反映する重要な情報の一つです。
しかし、大学実績だけを重視した学校選びは、必ず次のような議論につながります。
〇公立中学から都立日比谷高校(神奈川県立翠嵐高校)で東大へ行くのが一番コスパがいい
〇優秀な子はどんな環境にいても結局東大に行けるのだから、無駄な金をかける必要などない
〇せっかく高い金をだして私立にいれても、結局〇〇大学なら無駄な出費だ
〇高1で高校範囲を終了するので、あとは大学受験勉強に的を絞れる私立が有利だ
〇鉄緑会の指定校が重要だ
〇学校内で夏期講習や補習をやってくれる〇〇中学なら塾に行かなくてもいいのでお得だ
すべて「コストパフォーマンス」がかかわる話です。
子供の教育にコスパを持ち込むのには賛成できません。
私立(国立)中高一貫校の魅力は、そんな下世話なところにはないのですから。
ところで、知人に高校入試専門の塾の先生が何人もいるのですが、彼らはみな自分の子供たちは中学受験をさせています。
これが結論なのかな、と思います。