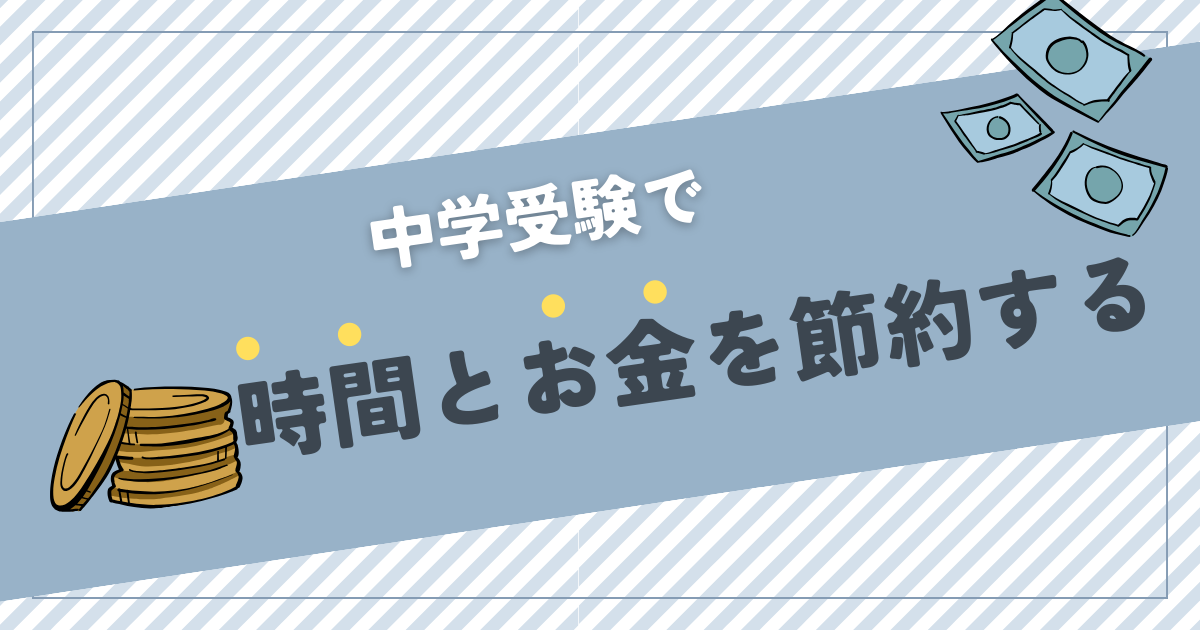
こちらの記事は、2024.3.17に加筆修正したものです。
1.はたして塾に行かずに中学受験は可能なのでしょうか?
中学受験を考える場合、必ず塾に通います。
みんなそうです。
なかには、中学受験をしないのに、高校受験を見据えて、小学生から塾に通う人もいます。
もちろん、どういった形であれ、学ぶことは良いことです。
塾に通えば、多くの学びが得られるのは間違いありません。
しかも、中学入試って、大人でも解けないような難しい問題が出るそうじゃないですか。
だから、中学受験をする=塾に通う
間違ってはいないと思います。
でも、天邪鬼な私は思うのです。
それって、思考停止ではないのだろうか?
ほんとうに塾に行かなければ中学受験はできないのだろうか?
自分の職業を全否定するような考えですね。
そこで、今回は塾に行かないで中学受験することについて書いてみたいと思います。
2.塾に求めるもの
別の記事で中学受験塾の選び方を書きました。
その時に、塾に期待するものとして次の5点をあげています。
(1)カリキュラム
受験用のカリキュラムを自分で作れ、そういわれたらほとんどの人が頭を抱えることでしょう。何せ中学受験で必要とされる学習内容を知らないのですから。その点塾におまかせするのは楽ちんです。プロの手で組まれたカリキュラムにしたがっていれば間違いはありません。
(2)教材
書店をのぞけば、参考書のコーナーのかなりの部分を占めて、「中学受験用」の参考書や問題集が並んでいるはずです。中学受験がこれだけ一般化すると、当然その需要に応えるべく各出版社が工夫をこらした教材を出版しているのです。しかし、これが逆に迷う原因となります。いったいどれを選べばよいのか、高い本が良いのか、安い本でも良いのか。塾の名前が入っているものがよいのか、それは関係ないのか。
ある時書店で見かけた光景です。小学生の娘を連れて中学受験参考書コーナーを熱心に回っている父親がいました。父親の手にはさきほどから1冊の問題集が握られています。どうやらSAPIXが出版している物のようです。ずいぶん長い時間そうして物色していた父親が、やはり最初に手にとったSAPIXの問題集を買うことにしたのでしょう。そこで初めて裏表紙の価格を見て言った一言がこれです。
「高っ!」
すぐに書棚に戻して手ぶらで書店を出ていきました。内容の良し悪しが判断できないと、とても高く感じるのですね。
(3)情報
中学受験を特集した雑誌、進学情報誌、塾のイベント、学校説明会、こうしたところからいくらでも情報は手に入ります。また、ちょっとWebをのぞいてみると、いくらでも情報が手に入る時代です。
しかし、いったいどの情報が正しいのでしょうか?
週刊誌の情報なら信頼できそうですが、よく見てみると、記者が直接取材した内容というより、教育評論家・受験アドバイザー・塾、そうしたいわゆる業界の人達の話をそのまま掲載しているものがとても多く見受けられます。もちろんその全てを鵜呑みにはできません。さらにWebに溢れている情報の多く(ほとんど)は信憑性がありません。もちろん塾に入れたとて信頼できる情報だけが得られるとは限りませんが、少なくとも対面で得た情報は信頼度が高くなることは間違いないでしょう。
(4)指導スキル
こればかりはプロにはかないません。親が子供の指導をすると、どうしても感情的になってしまうからです。
(5)ライバル
塾に行けば、同じような学校を受験する生徒が大勢います。また、日々の授業でも様々な競争が行われます。特に負けず嫌いの男子にそれをエンジョイする傾向が見られます。その結果、思わぬ成績向上を果たす生徒というものもいます。
このように、これらは塾でなければ得にくい、あるいは塾に期待するものだと思います。
逆に言えば、この5つが自分で用意できれば、塾に頼る必要はないということになりますよね。
例えていえば、海外旅行に行くときに、全部自分で手配する個人旅行とするのか、旅行代理店のツアーに参加するのか、の違いのようなものでしょうか?
ツアーは楽です。
お金さえ払えば、全部代理店がやってくれるのですから。
私のはじめての海外旅行が、学生時代に参加したヨーロッパツアーでした。
ドイツ・スイス・フランス・イギリスの4か国を、2週間ほどでまわるというものでした。しかし、今になって思い返しても、旅行の記憶というものが途切れ途切れでほとんど残っていないのですね。先日もその時同行した友人と話をしていて、「あのときのミュンヘンの日本料理はまずかったよな。」といわれて、「? 俺って、ミュンヘン行ったっけ?」状態でしたね。
それにくらべて個人手配の旅行は大変です。コロナ前にヨーロッパ旅行を企画したときです。パリでオルセーに行き、ギリシアで遺跡を見て、ロンドンで大英博物館に行く、そんなプランでした。飛行機以外に鉄道も駆使する予定で、各国の鉄道会社のHPから予約をしていたのです。ヨーロッパの鉄道の旅は楽しいです。軽食がサーブされたり、ビールが美味しかったりしますしね。とくに、ロンドンに行くならユーロスターに限ります。ヒースロー空港の入国審査の長蛇の列を回避できるだけでも価値があります。また、ホテルもなるべく地元系のこじんまりとしたところを選び、ロンドンではミュージカルのチケットもおさえました。
ところが、コロナで、すべて中止です。
エアもホテルも何もかも、カードで支払い済でしたので、一つ一つキャンセルしてお金を取り戻すのが、ものすごく大変でしたね。
それでも、旅行は個人手配に限ると思っています。
話がそれました。塾に通えば、あとは塾の指示にしたがってさえいれば、中学受験できる学力が身に付き、志望校に合格できる、そう思いますよね。(本当は違います)
適切な塾を選べば、思った以上の学校へ合格できるかもしれません。
それを、あえて茨の道を歩む理由とは?
3.塾無しの受験のメリット
それは、以下の3点です。
①親子の絆が深まる
②時間が節約できる
③お金が節約できる
②と③はわかりやすいですね。では、①はいったいどういうことでしょうか。
親子でカリキュラムを考え、親子で教材を探し、親子で学校情報を集める。
もちろんプロにまかせるように効率よくはいかないでしょうが、子供の学びの質が変わると思うのです。
そうして進学した学校なら、勉強をさぼったり登校拒否にならないような気がします。
「勉強しなさい!」とだけ声かけするより、はるかに得難い体験ができると思うのです。
理想主義すぎますかね?
そもそも私が自らの職業を否定してまで、塾に行かない中学受験のメリットを考えるようになったのは、海外駐在となってわが子の中学受験を模索しているお母さま方と話をしたことがきっかけでした。
〇滞在先には日本の塾が無いから日本の中学受験はできないとあきらめている
〇英語さえできれば帰国生入試でどこにでも合格できるという嘘の情報を信じている
〇理社は捨てて算国だけやらせればいいと誤解している
どう言ったらいいでしょうか、私がそこで感じたのは、自ら情報を取りにいこうとしないお母さま方の受身の姿勢だったのです。
「海外だから仕方がない」という恰好の言い訳のもと、子供の学習内容に無頓着な方が多かったように思います。
実は、これは日本国内でも感じていることです。
「子どもの中学受験を考えたのなら、まずは皆さんが入試問題を解いてみてください。」
講演会のような場で、こんな当たり前のことを言った瞬間、会場の空気がさあっと引いていくのが目に見えるのですね。別に親が解けるようになれと言っているのではありません。わが子が将来ぶつかる壁の高さ・厚さを身をもって体験するところから、受験に向かった生活がスタートすると思うのです。
塾産業がこれだけ発達したことの弊害なのでしょうね。
「全部お任せください」という塾がいかに多いことか。
もちろん信じてはいけません。
4.塾無し受験のデメリット
メリットばかり並べるのは公正さを欠きますね。ここではデメリットをあげてみます。
(1)親が大変
塾に丸投げしていたものを親がやるわけですから、それは大変です。
「わが子のために自分の時間を犠牲にするつもりはない」
「中学受験の研究などする気はない」
「入試問題を解きたくはない」
「自分には無理である」
もしそうしたお考えなら、この記事は全く参考にはならなかったですね。
ただし塾に丸投げして中学受験をするつもりなら、それは間違っているとだけはいえるでしょう。お子さんがどんな試練にぶつかろうとしているのか、それを理解するのはとても大切なことだと思うのです。
(2)効率が悪い
塾無しの大きなメリットとして「時間」をあげました。自宅学習は時間が効率よく使えます。その反面、親子で手探りしながらの学習となるため、どうしても「学習の効率」は下がると思います。今はしなくてもよい学習、回り道の学習をしてしまう可能性があります。全ての学習には無駄なことなど一つもない、そう割り切れればよいのですが。
(3)ライバルがいない
これが最大のデメリットでしょう。周囲にライバルがいない勉強は孤独な戦いです。親が上手に子供のモチベーションを維持する必要があります。
(4)不安である
塾という専門家の存在はとても大きいのです。中学受験の素人である親が主軸となって学習を組み立てていると、「はたしてこれでいいのか?」と不安になることはたくさんあると思います。しかしここは不安を子供に感じさせないよう振舞うしかありません。
(5)進学してから(ちょっとだけ)寂しい
中学校に進学してから、やはり最初のうちは「どこの塾だったの?」というあたりから会話は始まります。また、塾友同士でお互いの学校の文化祭に行き合う、そうしたこともよく聞きます。それらに全く加われません。まあどうでもよいデメリットですが。
5.見極め方
塾無しで行くか、塾に頼るか。
見極め方は簡単です。
入試問題を(親が)解いてみればいいのです。
偏差値表を参考に、お子さんを受験させたい学校をいくつか選びだし、10校分くらい解いてみてください。
それで、数年後の受験までのロードマップがなんとなく見えてくるのなら、塾無しのチャレンジが可能です。しかし、全く先が見通せないなら、塾に入れるほうが良いと思います。
あるいは、最初のうちは自宅学習で、模試の成績を見ながら、途中から塾に入れるというのもよいでしょう。
ただし、塾選びのところでも書きましたが、何度も塾を転々と移るのはおすすめできません。また、「所詮塾なんて利用すればいいだけだから」というスタンスで、講習だけ通わせる、といったやり方もおすすめできません。そうした姿勢では、塾のメリットを最大限に引き出す事はできないからです。