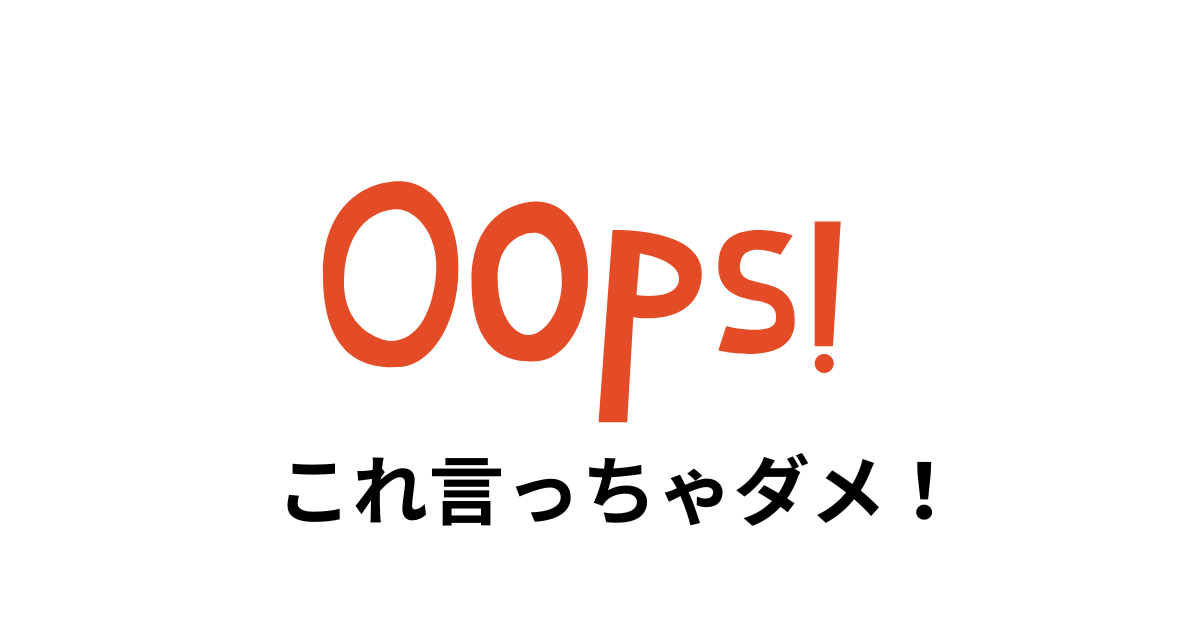
今回は、こんな言葉かけは逆効果!
そうしたNG声掛けワード集です。
- 「あなたが中学受験したいっていったんでしょ!」
- 「なんでこんな簡単な問題間違えたの!」
- 「そんな勉強姿勢だから、いつまでたっても成績上がらないのよ!」
- 「お兄ちゃんは(お姉ちゃん)はもっと勉強してたよ!」
- 「こんな成績では、どこにも受からないでしょ!」
- 「昨日やったばかりなのに、もう忘れちゃったの?」
- 「頭悪いんじゃないの?」
- 「そんなに勉強嫌なら、受験やめる?」
- 「そんなに勉強しないのなら、ゲーム取り上げるよ!」
- 「やれ」としか言わない
「あなたが中学受験したいっていったんでしょ!」
ああ、これはダメです。
考えてもみてください。
小学生の子どもが、いったいどうしたら自分から「中学受験する!」なんて発想を抱くのでしょうか?
どこからこの考えが浮かぶのでしょうか?
もちろん、自然発生的に心に浮かぶはずもありません。
どこかの誰かから、「中学受験したほうがいいよ」「中学受験するべきだよ」
「中学受験すると〇〇だよ」「公立中学に進学すると〇〇なんだよ」
なんて情報がインプットされたとしか考えられません。
もちろん、その「どこかの誰か」とは、誰のことかおわかりですよね?
そうです、親です。
つまり、親がそう望んでいるから、そう言ってほしいから、子どもは言うのです。
「僕、中学受験したい」と。
親の責任を子どもに転嫁してはいけません。
「お母さんとお父さんはあなたに中学受験してほしいって思っているの。その理由は・・・・・・・。」
このようにきちんと根拠を示しながらお子さんに向き合ってみましょう。
「なんでこんな簡単な問題間違えたの!」
子どもだって、間違えたくて間違えたわけではありません。
問題を解いているときは、正しいと思って解いていたのです。でも、結果として間違えてしまった。子どもはすでに考えているのです。
「どうして僕、こんな簡単な問題間違えちゃったのかなあ?」
そこに、かぶせるようにして親が言う。
「なんでこんな問題間違えたの!」
それに返す言葉を子どもは持ち合わせていません。
この言葉かけは無意味なだけでなく、逆効果です。
「この問題は、簡単だけれでも意外と間違えやすい問題だね。こうした簡単に見える問題を間違えないようにするためには、どういう点に気を付けたらいいのかな?」
こうして親子で考えてみましょう。
「そんな勉強姿勢だから、いつまでたっても成績上がらないのよ!」
勉強姿勢。
それって何ですか?
背筋を伸ばすことですか?
机にしがみつくことですか?
「勉強姿勢」などという曖昧なことを言われても、何をどう改めればよいのかさっぱりわかりません。
もし親から見た「勉強姿勢」がダメだというのなら、勉強姿勢というものがいったいどういうものなのか、そしてそれをどのように改めれば良いのか具体的に指摘しなくてはいけません。
〇背筋を伸ばして椅子に深く腰掛けなさい。足をぶらぶらさせないこと。椅子をがたがたゆすらないこと。
〇両手は机の上に必ず出しておくこと。ペンをくるくる回したりしないこと。
〇夕食が済んだらすぐに勉強を始めること。
〇学校から帰ったら、すぐに勉強にとりかかること。
〇最低でも30分以上は集中し続けること。トイレに何度も行かないこと。
〇周りで起きていることに気をとられないようにすること。
〇いわれる前に勉強を始めること。
たぶん、こういうことが言いたいのだと思います。しかし、本当にこれをわが子に強要するのでしょうか。こんなこと細かく指摘されたら、勉強に取り組む意欲など失せるというものです。
つまり、逆効果です。
「成績をあげるためには、勉強量に加えて勉強の質も大切なんだ。あなたの場合は、時間はかけているけれど、そこでこなす勉強量が多くないところに問題があるんだよ。まずは勉強スピードをあげる工夫を考えてみようか。」
同じ時間机に向かっていても、やる量がすくなければ効果はあがりません。効果が上がるスピード感で勉強することが、たぶん「勉強姿勢」ということなのでしょう。
「お兄ちゃんは(お姉ちゃん)はもっと勉強してたよ!」
あっ、これはダメですね。
この声掛けが最低であることは、さすがにわかりますよね?
兄弟は別人格です。上の子どもがどうだったかなんて、下の子どもには無関係な話です。
どうしても親というものは、中学受験に向かう子どもの指導経験が少ないのです。
まだ第一子なら、親もそうした経験がゼロであることを自覚していますので、問題は生じません。問題が生じるのは、第二子以降なのです。
ついつい上の子と比較してしまうのですね。
しかし、上の子のときうまくいった方法論がそのまま下の子に適用できるはずもありません。親だって、たった一人の指導経験しかない、いわばアマチュアです。
そんな狭い経験しかないのに、「上の子は〇〇だったんだから!」と下の子を責めるのはやめましょう。
実は、上の子の受験よりも下の子の受験のほうがうまくいかないことが多いのは、これが原因です。
(統計データではなく、あくまでも私の感触の話ですが)
「お兄ちゃんは〇〇が得意だったけれど、君は△△が得意だね。これは君の武器になる。この武器をもっと磨くことと、それから苦手な〇〇も普通のレベルにまでなれば素晴らしいと思うよ。そのためには何をどう工夫すればいいのか、一緒に考えてみようか。」
兄には兄の、弟には弟の得意分野というものがあるはずです。得意を伸ばし、不得意を
不得意でなくす努力をどのようにすればよいのか。それを考えるだけのことだと思います。
「こんな成績では、どこにも受からないでしょ!」
ああ。
ひどいですね。
たとえどんな成績であっても、受かる学校はあります。
お子さんの成績がその状態なら、その成績でも合格が見込める学校を探すのが正しい親のあり方だと思うのです。
むやみに子どもに幻想を投影するのはやめましょう。
「今の成績では、A中学やB中学への合格は難しい。でも、C中学やD中学ならがんばれば届くかもしれない。まずはそこ目指して頑張ろうよ。」
このように声掛けしてほしいです。
「昨日やったばかりなのに、もう忘れちゃったの?」
子どもは忘れる生き物です。何度教えても、すぐに忘れます。私は、最低でも5回は同じ話を授業でします。6回目くらいからやっと、「あっ、それ習ったかも。」と言ってくれます。
そんなものです。
どうして世の中の大半の親は、子どもに完璧を求めるのでしょう?
一度見たら、一度聴いたら、一度解いたら絶対に忘れない、二度と同じ間違いをしない。
そんな生徒なら、中学受験勉強は1年も必要なくなりますね。
私の仕事もあがったりでしょう。
「そうか、忘れてたか。それなら、今覚えよう。」
こうして何度も覚えれば済む話です。
「頭悪いんじゃないの?」
わが子に向かって、こんなことを言う親はいないと信じたいです。
子どもの頭脳の設計は、両親の設計図からできています。
「パパとママの子どもの頃より、今の君のほうがはるかに難しいことやってるね。それを出来るなんて、凄い!」
こうして子どもを褒めてあげられる親でありたいと思います。
「そんなに勉強嫌なら、受験やめる?」
本当にやめていいのですか?
「うん、それなら僕勉強嫌いだから受験なんか止めるよ。」
お子さんがこう言ったら、そのまま素直に受け止めるのですか?
勉強が好きな子どもはいません。(正確にはごくわずかいる)
それでも親の期待を敏感に感じ取って頑張ろうとはしているのです。それなのにいきなり梯子を外すのやひどいです。
「勉強が嫌なのはしかたないよ。誰だって嫌なものだから。お母さんんだって好きじゃなかったもの。でも、今やっているこの勉強は、絶対役に立つ勉強だから。だから、がんばってみよう。」
受験のための勉強ではありますが、教養を高める将来に役立つ勉強でもあるのです。
「そんなに勉強しないのなら、ゲーム取り上げるよ!」
これは今までの話とは少々異なります。
そもそも、ゲームなんて与えていたのですか?
ゲームは、子どもにとって「百害あって一利なし」の見本のようなものです。
ゲームは、才能ある大人たちが、「いかにハマルか」「いかにやめられなくなるか」だけを考えて、全能力を注ぎ込んで作っているのです。
小学生の子どもが、自力で制限できるはずがないのです。
麻薬と一緒です。
そんな麻薬=ゲームを与えておきながら、「いつまでゲームばかりやってるの!」はないですよね。
もし愚かにも与えてしまったのなら、即座に取り上げて捨てるべきです。
私がこのような論調で話をすると、反論が聞こえてきます。
「ゲームにだって深い世界観が広がっているものも多い」
「ゲームから友情や仲間の大切さが学べるんだ。」
「実社会でできない体験をシミュレートすることができるのがゲームの醍醐味」
「勉強に役立つゲームもたくさんあるよ」
「くだらないアニメを見るより、ゲームのほうがはるかに頭を使う」
「脳の発達に役立つっていうよ。」
「まわりが皆やっているから、やらないと仲間外れになる」
他にもいろいろありますね。
まあ、全てこじつけです。
ゲーム以外から学べることの方が多いですし、ゲームで脳が発達するのか破壊されるのかは何ともいえないと思います。ゲームをやらないことで仲間外れになるような仲間などこちらから願い下げです。
子どもにゲームを与えない良識を持つ親であってほしいと願います。
(私の知人に、子どもとゲームを一緒にやりたくて、最新のゲーム機・アプリを嬉々として買ってきてわが子に与えていた父親がいましたが、子どもは全く興味を示さないと嘆いていました。この子どもは、最難関私立中高から最難関大学へと進学したのは偶然ではないと思います。まあレアなケースです。)
「やれ」としか言わない
みなさん、「勉強しなさい!」「早く始めなさい!」とは常に口にします。しかし、「そこでやめなさい」とは声掛けしないのですね。
子どもは自分の時間のコントロールが不得手な(というより全くできない)ものです。「始め!」の号令ばかりかけて、「終わり!」の号令をかけるのを忘れていませんか?
始めたら終わらなければいけません。
算数を始めたら、1時間後に終わらせましょう。次に国語をはじめたら1時間後には終わらせましょう。こうして時間スケジュールをコントロールすることが大切なのです。