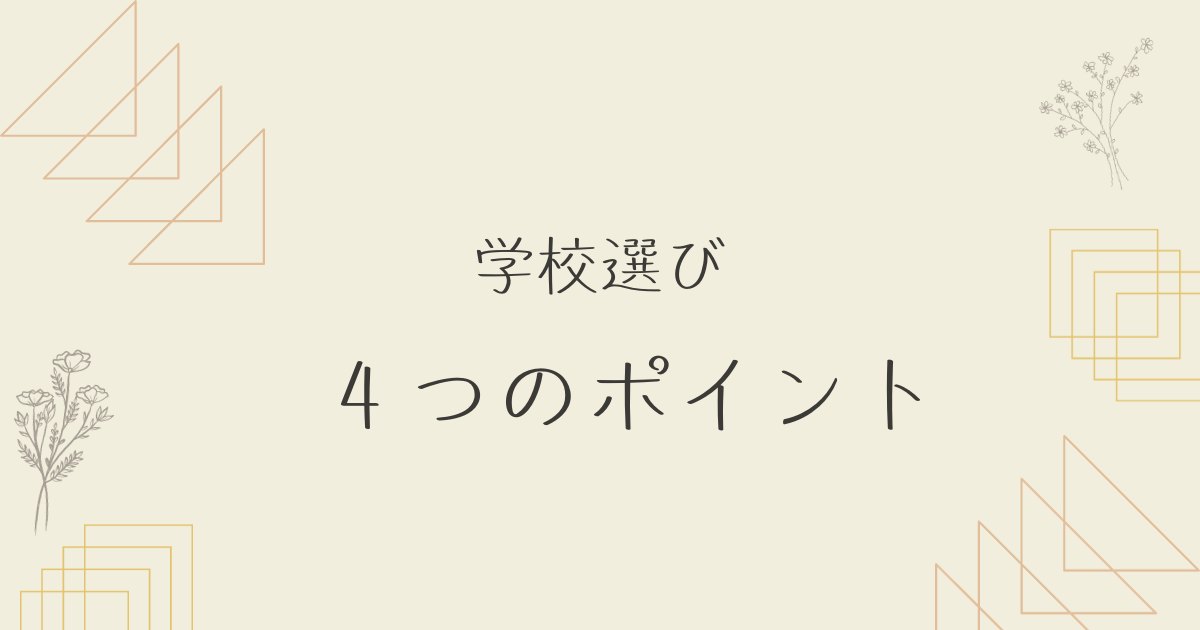
以前に学校選びのポイントについて書きました。
また、重要なポイントについてこの点についても書いています。
1.立地
2.共学/別学
3.偏差値
4.得点力
今回は、その続きとして、施設・伝統・大学実績について書いてみようと思います。
1.施設
いろいろな学校にお邪魔する機会があるのですが、最近の学校はどこもきれいでおしゃれですね。
日の差し込むカフェテリア、図書館のイメージを覆すようなライブラリー、大学顔負けの設備を整えた実験室など。
ロビーや廊下に生徒がくつろげるベンチが設置されていたりもします。
自分が中高時代を過ごした古びた校舎を思い出すと、もう一度生まれ変わってこんな学校で学生時代を過ごしたいと思わせられるほどです。
だが、そこって重要なのでしょうか?
もちろん、校舎は汚いより綺麗なほうが、古いより新しいほうがいいに決まっています。
宇宙に興味のある受験生なら、天体望遠鏡のドームやプラネタリウムまで備えた学校に行きたいかもしれないですし、水泳をやりた受験生なら、プールのない学校はあり得ないでしょう。
学校にとって、施設をリニューアルしたり新設したりすることは、生徒募集に大きな効果があるといいます。
最近のトレンドは、図書館とICT設備を充実させることのようです。
昔ならプロジェクターが教室に設置されているだけで感心したものですが、今や電子黒板も標準装備のように当たり前になってきました。
幕張メッセやビッグサイトで年に何度も開催されている教育ICT系の展示会に足を運ぶと、熱心にブースを見て回っている学校の先生方を大勢見かけます。
新校舎建設を公表すると受験生が増えるということもよく耳にします。
目に見えるそうした施設は、入学案内のパンフレットやHPでもアピールしやすいポイントなのですね。
しかし、学校の予算は限られています。施設に予算を回せば、他にしわ寄せがいかないか心配してしまいます。
私がいくつか訪れた学校を紹介します。
※いつものように私の主観(多分に偏見)です。どこかの学校を推す意図も逆の意図もありません。
(1)訪問記その1 「共学化したことで、人気が沸騰した都心の学校」
低迷していた女子校が共学化したことで一気に人気校となる。最近よくみかける事例ですね。
その学校もそうした学校の一つです。
実は、共学化する以前に、校長先生と教頭先生にお会いしたことがあります。校長先生は底辺の都立高を立て直した実績を買われて校長に就任された方でした。
「まずは挨拶を徹底するところからはじめています。」
そう語られていましたが、結局は立て直すことができず、校長も校名も変わり、新たな学校に生まれ変わったのですね。
都心の学校はみなそうですが、ここも敷地面積は狭い学校です。校庭とよべるものはありませんが、体育館や屋上グラウンドなどがもうけられています。
8階建ての建物には明るいカフェテリアが2か所もあり、実験室には3Dプリンターが並んでいます。
私が訪れたときは、カフェテリアの1つで、保護者に対しクラブ活動の海外遠征の説明会が開かれていました。
帰国生の受け入れも多く、国際教育に力を入れている学校です。廊下や教室の壁には、All Englishで書かれた生徒の制作物が掲示してあり、まるで海外の学校のようでした。
ただ、その制作物をよく見てみると、実に拙いのです。
中1の制作物かと思っていたら、中3のものでした。
この印象は私だけのものではなく、ある受験生のお母さまからも同じような話を聞きました。
受験生保護者向け説明会に足を運んだそうですが、多くの保護者の方々が「さすがね。」と感心されていた英語の掲示物のレベルが高くはないことに気が付いたそうです。そのお母さまは海外留学経験もあり英語が達者な方でしたので。
校内はとても明るくきれいな学校です。ただ、私の感想としては、校舎全体が見通しも風通しも良すぎる気がするのです。
先生の目が行き届き過ぎるというか、生徒の逃げ場がない印象を受けました。
中高生なんて、親や学校には秘密にしておきたいような経験の1つや2つはするのが当たり前だと思います。
もちろん節度はわきまえねばなりませんが、そうした経験もまた、子供の成長の糧となると思うのです。
この学校では、そうした経験の積みようもない、とても「良い子」が量産されるような気がしました。
もちろん、この感想は、中高時代に悪いことばかりしていた私の個人的な感想なので、賛同はしていただけないでしょうね。
(2)訪問記その2 都心にある女子校
この学校は、紛れもない伝統校で、都心の一等地に立地しています。
併設の短大をずいぶん前に閉じたため、かつての大学の敷地と設備をそっくり中高が利用できるという、実に恵まれた環境にあり、使われていない実験室などがあるほど余裕がある作りです。
理系教育にも力を入れています。
率直な感想としては、高校生の研究発表としては、幼い印象でしたね。
ただし、入学時の学力を考えれば、頑張っているといえなくもありません。
(3)訪問記その3 都心にある女子校
訪れたのは、古い歴史を誇る人気校の一つですが、校舎は近代的な9階建てです。
図書室にお邪魔しました。
吹き抜けの1階に図書室はあり、とても出入りしやすい環境です。
司書の先生が読書に力を入れているということで、充実した蔵書が目を引きます。今おすすめの本などが手書きのポップで飾られていたりもしています。
書架にならぶ本を見ると、新書を中心に、なかなか難しい本が並んでいます。自然科学系の本も多く、理系教育にも力が入っていることがうかがえました。
さすがだな、と思い手にとってみると、どの本にも開いた痕跡が無いのです。
もちろんすべての本をチェックしたわけではなく、たまたま目についた数冊に限った話ですが。
真っ新の本だけがむなしく並ぶ図書室でした。一角だけ、手ずれのした大人気の本がありました。「漫画・日本の歴史」です。
今読むべき本のリストがわかりやすく掲示されており、司書の先生方の情熱は伝わりました。
その情熱にいずれ生徒達が応えてくれる日がくることでしょう、きっと。
後日談:その学校の卒業生のあるお母さまに図書室の話をしたところ、「うちの学校に図書室なんて無かった」と断言されていました。まさか無いはずはないので、一度も足を運ばなかっただけだと思います。
校舎新築にともない、図書室を一番目立つ1階にした理由がわかりました。
ハコモノ行政の話ではないですが、施設を作るのは簡単です。お金さえかければいいのです。そこに魂をいれられるかどうかは、別問題なのですね。
2.伝統校の魅力
「100年以上の歴史を誇るA校と、創立間もないB校、先生ならどちらを選びますか?」
これは、ある保護者からの質問です。
答えは簡単。
「そんなものわかりません。」
それはそうです。
立地も教育方針も先生も生徒も、すべてが異なる2校を、伝統の有無だけでは選択できるわけがありません。
でも、こう食い下がられました。
「本当に迷っているのです。親子で、どちらの学校も同じくらい気に入っているのです。」
そこで、こうお答えしました。
「自宅から通学時間の短い学校がよいと思います。」
しかし、どちらも同じだというのです。しかたなく、こうお答えしました。
「伝統校をお勧めします。」
学校を新しく作るというのは、想像できぬほど大変な事業だと思います。
まして、教育環境が整わぬ時代(明治時代)に、新たな学校を設立することには多くの困難があったことは容易に想像できます。
一人の(あるいは複数の)強力な個性をもつ人物がおり、教育に対する強い信念でまわりを動かしていくのです。
その人物のまわりには賛同者が集まり、出資者も動きます。
その理念に惹かれて生徒が集まるのです
ほとんどの学校がこうしてできてきたはずです。
そして、その理念のもとに集まる教師・生徒達が何サイクルも続いて、100年を超す伝統が形作られていく。
伝統校の魅力とは、そういうものです。
この、目には見えぬ伝統の重みのようなものを、感じ取れるかどうかが、伝統校を評価できるかどうかの分かれ目なのでしょう。
もちろん、古ければよいというような単純な話ではありません。しかし、伝統校の校風には、すでに確立されているという安心感がありますね。
「訳のわからぬルールを守らされたり、先生も厳しくて、思い出すのも嫌なんです。」
と言っていたのは、都内有数のカトリック伝統校を卒業した生徒の言葉です。
ルールには理由があり、良い先生ほど厳しい。
6年通ってもそれがわからなかったということは、その学校が合っていなかったということなのでしょう。
「この学校の自由って、成績が良い生徒の方を向いた自由でした。」
これは、自由な校風で知られるプロテスタント伝統校の卒業生。
彼女は、完全に自由をはき違えてしまったのですね。
髪型・服装、すべてが個人の自由に任されている学校であり、彼女も十分にその自由を満喫しました。ただ、勉強を全くしなかっただけです。
己を律することの意味を知らぬ生徒には合わなかった学校でした。
そうした歴史の一員になることに生徒自身が誇りをもつかどうか、じっくりと見極めてほしいと思います。
3.新興校の魅力
新興校といっても様々です。
全くの新設校もあれば、女子校が共学化して名前を変えてリニューアルしたもの、高校が中学を併設したものなどがあります。
そこで、視点を変えてみましょう。
その学校は、市場の需要に応えて作られたのか、それとも創立側の意志が先行したのでしょうか。
A:需要に応えてつくられた学校
例えば、英語教育熱の高まりを受け止める目的でAll Englishの授業を売りにした学校であるとか、バカロレアコースを併設した学校などがあげられるでしょう。
国内の閉塞感を背景とし、我が子には英語を駆使して世界で活躍してほしいという親の願いをくみとる形で増えてきました。
海外大学進学実績を誇り、海外留学制度が充実しているのも共通した特色です。入学案内に横文字が多いのも特徴です
海外帰国生に人気の学校も多く、まさにこうした生徒のニーズをくみ取って作られた学校といえるでしょう。
共学の進学校も、このジャンルと考えてよいでしょう。
それまでは、首都圏では共学は大学附属校ばかりで、進学校といえば、千葉の東邦大東邦、神奈川の桐蔭、都内では国立の付属くらいしかありませんでした。
渋谷幕張をはじめとして、続々と誕生した共学の進学校は、そうした学校を求めるニーズに応えたとみることができるでしょう。
B:供給側の意志が先行してつくられた学校
現行の教育に飽き足らず、自分の強い思いを実現するために作られる学校です。
教育者が主体となってつくられる学校ですが、実は、最近はあまり見かけません。
すでに多様な教育を実践する学校があり、今ここで新しい教育理念を打ち立てる余地がないのでしょう。その理念はすでにどこかの学校で実現しているのだから。
そのかわりによく見かけるのが、ビジネスとして作られる学校です。
定員割れが続き、閉校の危機を迎えた女子校が、創立理念をきっぱりと捨て、共学化へと舵を切る。こうした学校は、むしろ前述のAに分類されますね。
いずれにせよ、新興校の魅力とは、現在進行形の魅力に他なりません。
自分たちがこれから伝統を作っていくのだ、という高揚感は捨てがたいと思います。
伝統校にありがちな理不尽なルールや縛りが少ないことも魅力です。
また、制服が今風であったり施設が充実していたり修学旅行が海外であったりと、生徒本人が喜びそうな特色もあります。
保護者にとっても、新しい教育が標榜されているのは好ましく思えるでしょう。
しかし、現在進行形ということは、入学時から卒業時で大きく学校の方向性が替わることもあります。実際に、情操教育も重視した学校だと思って入学したら、いつの間にか受験予備校化してしまった、などという声も聞いたことがあります。
また、新興校の多くが、学校の魅せ方に長けていることには注意してください。
広報担当の先生の弁舌が冴えわたっていることも特徴だからです。
耳に心地よい言葉の背後にある本質をしっかりと見抜く必要があるのです。
4.大学進学実績
進学校の場合、6年後の我が子の行く末が気になります。
それ故、大学進学実績を誇る学校も多く、実績を上げるために無料の夏期講習などを充実させている学校もまた多くあります。
それに対しては、「実績は塾・予備校が作ったもので、学校の手柄ではない」だとか、「できる生徒が集まっていただけ」といった反論もありますね。しかし、この反論は間違っています。
教師は生徒に育てられる。
以前こう書きました。
高い進学実績の学校では、当然生徒の勉学における熱意もレベルも高いです。
そうした生徒を指導する立場の教師も、日々の努力が求められます。つまり、進学実績の高い学校の先生方の水準も高いと考えられるのです。
さらに、高い目標を持とうとする生徒同士の醸し出す空気感のようなものも重要です。
考えてみてください。例えば100%が内部進学する大学付属校で、一人だけ外部受験するとしたら。いくら塾に通ったところで、相当困難な受験になることでしょう。
目標をもって勉強するのは当たり前、そういう環境を評価すべきなのです。
輝かしい大学進学実績の学校と、そうでない学校では、教師の力量も生徒の熱量も異なるのはあたりまえですね。
とくに前述した新興校や宣伝上手な学校を選ぶ際には、大学実績は注目ポイントです。
口ではいくらでも耳障りの良いことは言えます。しかし、大学実績を見れば、その学校の生徒のレベルというものが一目瞭然です。
国際教育を標榜し、いかにも世界に羽ばたけるような案内がHPにのっていても、実際の進学先は国内の大学ばかり、海外の大学実績も良く見てみれば誰でも入学できるような大学名が少し載せられているだけ、そうした学校も見かけます。
こうした話をすると、必ずこう反論されるものです。
「まだ歴史が浅いから。6年前はそんなにレベルが高くなかったので。これからは伸びますよ。」
そうかもしれません。そうかもしれないのですが、なんだか言い訳のようにしか聞こえないのは私の性格の悪さ故なのでしょうか。
それなら、確かな実績が出るようになってから選んだほうがよいと思ってしまいます。
5.ブランド
〇医科歯科大学でも満足できない?
〇祖母が喜んでくれた
〇大人になってから有難みがわかった
〇海外で母校の卒業生に助けられた