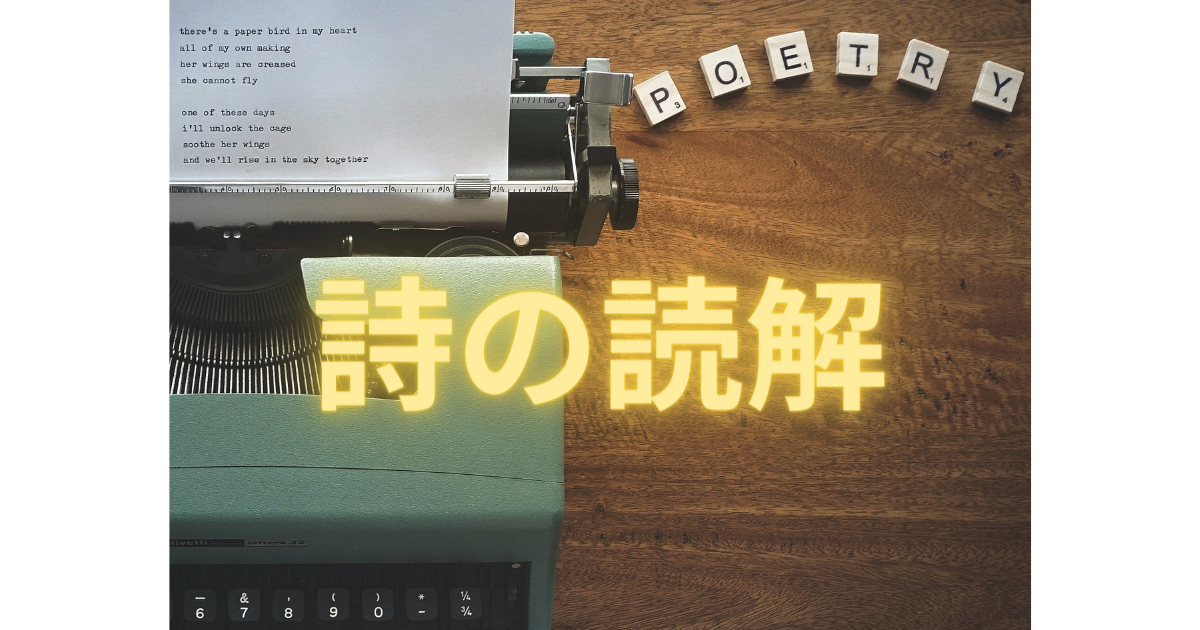
以前の記事で、「詩の読解はまず俳句から」と書きました。
しかし、それだけではどうも不親切だったようです。
今回はさらに発展させた内容を書きたいと思います。
韻文読解の注意・・・フィーリングで解かない!
韻文に限らず、どんな文章にも共通した注意です。
「なんとなくそう思った」
「〇〇っぽいイメージだと思った」
論説文・物語文では禁じている読解のやり方です。ところが韻文(詩)になると、なぜか皆フィーリングで解こうとするのですね。
その理由は簡単です。
そもそも字数の少ない韻文は、読者の想像力を刺激することで成り立っています。
例をあげましょう。
古池や蛙飛びこむ水の音
いわずとしれた松尾芭蕉の句です。芭蕉の句の中で最も有名なものかもしれません。
蕉風の俳諧を確立した句ともいわれています。
無粋を承知で解説します。
もともと和歌の世界では、蛙が登場するときはその鳴き声に注目するのが普通でした。
例えば万葉集には蛙の句がたくさん詠まれています。
かはづ鳴く 神奈備川に 影見えて 今か咲くらむ 山吹の花
かはづ鳴く 清き川原を 今日見ては いつか越え来て 見つつ偲はむ
芭蕉は、あえて蛙の鳴き声ではなく、飛び込んだ水の音にフォーカスしました。また、和歌の世界では蛙とワンセットで登場することの多い山吹も使いませんでした。
「古池」についてはわかっていません。芭蕉庵の生け簀であるとか、どこそこの池であるとか、いろいろな説が出ています。なかには、実在しない空想上の池であるという意見も。また、蛙の種類も不明です。
こうした解釈がどうでもいいことに思えてくるところが、この句の魅力(凄さ)なのではないか、というのが私個人の意見です。
どんな池だっていいじゃないですか。どんな蛙だっていいじゃないですか。
この句を読んだ人の頭に浮かんだイメージ、それこそが唯一無二の解釈なのだと思います。わずか17文字の句から無限のイメージが存在するところが俳句の魅力です。
韻文は読者のイメージを喚起するように書かれるのです。
だからこそ、正しい印象というものは存在しません。どんなイメージを持とうと、それは読者の自由です。この芭蕉の句だって、「最悪の駄作」という評価を下す人もいるくらいです。
このように本来解釈は自由であり無限に存在すべき韻文を読解するというところに無理があります。
しかし、文句を言ってもはじまりません。
まずは自分のフィーリングを捨て去ることから始めましょう。
韻文の技法を知る
韻文には、いくつかのテクニックが使われています
短い文で表現するための技法です。
俳句にある「季語を入れる」なんていうのもその一つですね。
これらのテクニックのうち、基本的なものを最初にマスターしましょう。そうすると読解がやりやすくなるはずです。
1.比喩
最も多くみられる、そして最も重要な表現です。
空を見上げたとして、泣き出しそうな空に見えるのか、抜けるような青空なのか、羊のような綿雲が浮かんでいるのか、雲間から矢のような光が降り注いでいるのか。
比喩には以下の種類があります。
①直喩
「まるで〇〇のようだ」
これは簡単ですね。
「お盆のような月」
童謡にありますね。そのまんまの意味です。
「綿も無き 布肩衣の 海松(みる)のごと わわけさがれる」
貧窮問答歌です。綿も入っていない粗末な服が、まるで海藻のように垂れ下がっているのですね。
直喩はわかりやすさが身上です。
しかも、そこには「そのように例えている作者」の存在も感じ取れます。
「花子ちゃんの目はまるで宝石のように輝いている」
こう書かれると、花子ちゃんのことを見つめている(たぶん好き)太郎君の存在が感じ取れませんか?
②暗喩(隠喩)
「花子ちゃんの目は宝石だ」
言い切りましたね。
もう既定の事実のように、「花子の目=宝石」と言い切っています。そのため、そこには語りてである太郎君の影があまり感じられません。
この直喩と隠喩の、似ているけれど微妙に異なる効果を感じてほしいのです。
「綿のような雪が降ってきた」
「綿の雪が降ってきた」
これならどうでしょう?
前者には、少しの遠慮が感じられます。「私には綿のように感じられたんです」といっているのですね。ところが、「綿の雪」と書かれると、遠慮はありません。
もう雪=綿なのです。有無を言わせず言い切ってしまうところに隠喩の強さ・面白さがあります。
③擬人法
「風がささやく」
「小鳥が歌う」
「泣き出しそうな空」
「ペンが走る」
このように人間ではないものを人間に例えるのが擬人法です。
擬人法には3つの種類があります。
◆動作
上にあげた例はすべてこれです。
人間がする動作に例えるものですね。
その他にも、「花びらが舞う」「大地が怒った」といったものが相当します。
◆状態
状態とは、外見のことです。
「貴婦人のようなバラ」
「やんちゃ坊主のような犬」
◆性質
「この車のエンジンは気難しい」
「鍵がバカになった」
「神経質な時計」
さて擬人法の効果とは、読者にイメージを伝えやすくするというものですね。
より生き生きとした文章を狙うものです。
「道がつづら折りになって、いよいよ天城峠に近づいたと思う頃、雨脚が杉の密林を白く染めながら、すさまじい早さで麓から私を追って来た。」
もう、うなるしかありません。
このわずか1文で、一気に天城峠に連れて行かれる気がします。
「雪国」の冒頭はこれでしたね。
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。」
どうしたらこんな文章が書けるのでしょう?
ぜひ、お子さんにも川端康成を読ませてほしいと思います。
私のおすすめは、「掌の小説」という短編集です。
美しい日本語に酔いしれてください。
2.倒置法
これも多くみられる技法ですね。
「花子が笑った。」
「笑った、花子が。」
前者では、普通に花子が笑ったんだな、ということがわかるだけです。
しかし後者では、より強い印象が残ります。
もしかして花子はめったに笑わない子なのかもしれません。あるいは何か辛い出来事があってしばらく笑っていなかったのかもしれません。そんな花子がついに笑った、やっと笑った、そんな想像が膨らみますね。
この倒置法は、韻文以外でも普通に使われています。しかし、韻文で見かけることが圧倒的に多いのです。
韻文は、短い字数でリズミカルに書かれるものです。だから、こうした技法を使うことで、イメージを広げやすくなるのですね。
主語 → 目的語 → 述語
僕たちは 明日に備えて 早く寝た。
主語 → 述語 → 目的語
僕たちは 早く寝た 明日に備えて。
もしかして明日はテストなのかもしれません。それとも遠足か。そうした明日の何かに備えて早く寝たのですね。
倒置することで、早く寝たことが強調されました。よほど大切なイベントがあるように思えてきませんか?
3.体言止め
いわゆる「名詞止め」です。
「ある晴れた冬の日。散歩してみた近所の道。いつものように吠えてくる白い犬。」
倒置法と似ていますが、語尾が名詞であることに注目しましょう。
さて、この体言止めですが、使いすぎると文章として稚拙になります。日本語の文法としてはイレギュラーな用法だからです。韻文のようなリズムを重視する文では有効ですが、普通の文章では多用してはいけません。
上の例は、これくらいに直しておきましょう。
「ある晴れた冬の日に、散歩してみた近所の道。いつものように白い犬が吠えてきます。」
ここでは「近所の道」が強調されていますね。
「ある晴れた冬の日。私は近所の道を散歩してみた。いつものように白い犬が吠えてきます。」
これは、「冬の日」が強調されています。
このように、「ここぞ!」というところで使うのが効果的な技法です。
4.対句
韻文特有の技法です。
ここでは、例として漢詩をとりあげます。
日本語の技法は、その多くを漢文から取り入れています。
ちょっとここでオリジナルにあたってみましょう。
江碧鳥愈白
山青花欲然
今春看又過
何日是帰年
杜甫の「絶句」です。
横書きだとどうも雰囲気が出ませんね。

こうみどりにして鳥いよいよ白く
山青くして花もえんと欲す
今春みすみす又過ぐ
いづれの日にかこれ帰年ならん
川は青緑色で、鳥はいっそう白い
山は青く 花は燃えるような色だ
今年の春も また過ぎてしまう
いつになったら故郷に帰ることができるのか
さて、ここでの対句はわかりますね
江ー山
碧ー青
鳥ー花
白ー然
漢詩に親しむと、韻文はがぜん面白くなってきます。
5.くりかえし
これも韻文独特の技法です。
ここでは、山村暮鳥の「風景 純銀もざいく」を取り上げるしかありませんね。
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
かすかなるむぎぶえ
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
ひばりのおしやべり
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
やめるはひるのつき
いちめんのなのはな
野暮を承知で解釈すれば、見渡す限りの一面の菜の花の情景を読者に強烈に印象づける詩です。そこに、
「かすかなるむぎぶえ」
「ひばりのおしゃべり」
「やめるはひるのつき」
が挿入されることで、聴覚が広がり、縦方向にもイメージが広がります。
6.俳句の技法
俳句はわずか17文字の詩です。
そのため、独特の技法が発達しました。
ここでは2つだけ挙げておきます。
季語
俳句は季語を必ず入れなければなりません。
このルールが俳句を奥深いものにもするのですが、敷居を高くもします。
6月の季語を並べてみました。
仲夏、夏至、皐月、田植時、梅雨寒、入梅、白夜、半夏生、梅雨、梅雨雷、梅雨曇、雨乞、雨休み、黍蒔、早乙女、菖蒲酒、菖蒲人形、菖蒲の根合、菖蒲の鉢巻、菖蒲引く、菖蒲葺く 菖蒲湯、神水、新真綿、田植、田植唄、田下駄、手花火、蛍籠、蛍狩、牛蛙、蚕蛾、蛇衣を脱ぐ、鳶尾草、藺の花、桜桃の実、オリーブの花、木耳、金魚草、桑の実、楮、百日紅、菖蒲、除虫菊、どくだみ、昼顔、ラベンダー
このあたりはまだわかりやすいほうです。
こうした季語、しかも「聞いたことのないような」「何のことかよくわからない」季語を入れなくてはいけないような気がしてきますね。これはテレビ番組の悪影響だと思います。
しかし、以下の句を見てください。
菖蒲湯も 小さ盥で すましけり (小林一茶)
紫陽花や 藪を小庭の 別座敷 ( 松尾芭蕉)
シンプルでいいですねえ。
句切れ
これも俳句独特のルールです。
切れ字「や」「かな」「けり」がついているところで句切れとなるのです。
意味やリズムを切る働きがあるのですね。
ただし、必ず切れ字があるとは限らないところがやっかいです。
「古池や 蛙飛びこむ 水の音」
これは簡単。初句切れですね。
これを「古池に 蛙飛び込む 水の音」 として比べてみると、「や」の効果が実感できると思います。
「やれ打つな はえが手をすり 足をする」
これは初句切れです。
切れ字が使われていませんが、「打つな」が命令形なので、これが文末、つまり句切れとなります。
韻文の読解法
詩・俳句を見たら、まずはそこで使われている技法に注目しましょう。
技法を使うということは、何か理由があるということなのです。
何を強調しようとしているのか、何を読者にイメージさせようとしているのか。
それを一つずつ解きほぐしていくことが、韻文の読解の基本となります。
正直、おもしろくはないです。
詩の雰囲気をぶち壊してしまいます。
しかし、読解をすすめていくと、次第に韻文の面白さが見えてくると思います。